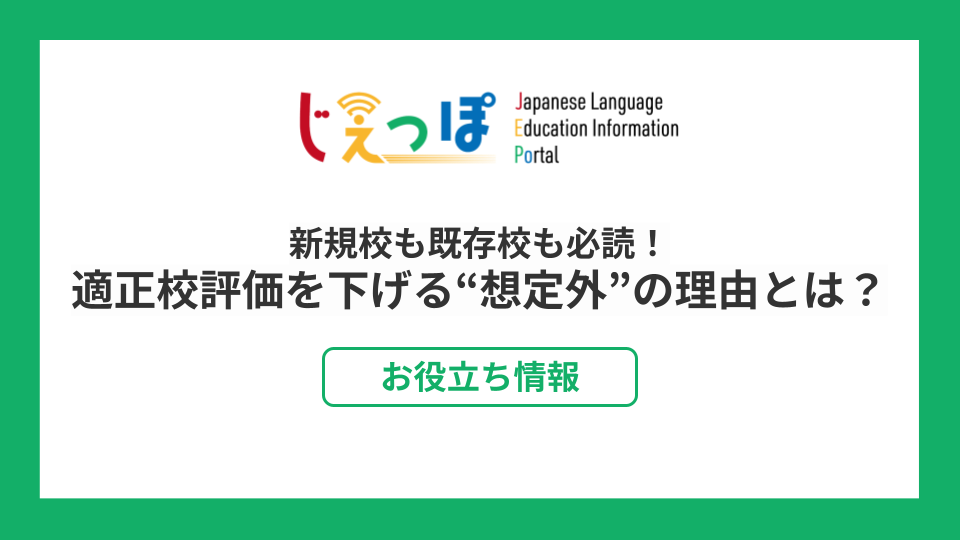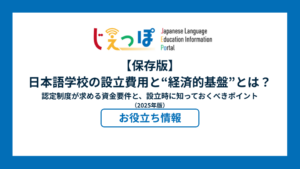「うちは適正校だから大丈夫」
――そう思っていませんか?
実は、長年適正校として運営してきた学校でも、“思わぬ理由”で評価を落とすケースが後を絶ちません。
退学者の報告漏れ、届出のわずかな遅延、進学先での元学生の不祥事……。
これらは日常の小さなミスに見えますが、一度の指摘でクラスⅠから外れる、場合によっては適正校の基準を満たさなくなることもあります。
もちろん、新規参入校にとっても初年度の運営体制は翌年以降の判定に直結します。
つまり適正校制度は、新旧問わず学校運営の生命線なのです。
本記事では、制度の基本とメリットに加え、既存校でも見落としがちな判定ダウンの要因とその防止策を具体的に解説します。
「そんなことで?」が命取りになる前に、ぜひ貴校の運営体制を点検してください。
認定校として日本語学校を設立したい方へ
認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、
無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。
対象:設立検討中/制度に不安がある方
“適正校”の意味と選定のしくみを押さえよう
まず、「適正校」の定義を正しく理解しましょう。
適正校とは、入管(出入国在留管理庁)が「留学生の在籍管理が適正に行われている」と認めた教育機関のことです。
これは一種の評価制度で、毎年1回見直しが行われ、各教育機関の運営状況が厳しく審査されます。
審査の基準は主に以下の通りです。
- 問題在籍率が低いこと: 不法残留、在留資格の取消、退去強制などになった学生(問題在籍者)の割合が、全在籍者数の5%以下であること。
- 各種届出が適切に行われていること: 学生の退学・除籍・所在不明などが発生した際、入管へ義務付けられている届出(法第19条の17に基づく届出)が、遅滞なく正確に行われていること。
- その他、在籍管理上の不適切な事情がないこと: 上記以外にも、入管からの指導内容や、学生の受け入れ体制全般が総合的に評価されます。
これらの基準を満たすと「適正校」に選定され、さらに厳しい基準(例:3年連続で問題在籍率1%以下など)をクリアすると、より優遇措置の大きい「適正校(クラスⅠ)」に選定されます。
適正校になる3つの大きなメリット
適正校は単なる「お墨付き」ではありません。
事務効率化・経営安定・信頼性向上という、実務と経営の両面に直結する効果があります。
しかも、意外と知られていない優遇措置も含まれています。
メリット1:COE申請書類が大幅に簡素化
非適正校の場合、経費支弁者の収入証明、預金残高、その形成過程の立証資料など、膨大な書類を準備・確認する必要があります。
しかし、適正校の場合、これらの書類の多くが免除されます。特に「クラスⅠ」なら提出は申請書など数種類のみ。結果として職員の事務負担が大幅に減り、学生サポートや教育活動により多くの時間を割けます。
メリット2:45号報告の一部免除
日本語教育機関は毎年、告示基準適合性の点検結果を入管に報告する義務があります。
しかし、適正校クラスⅠに選定されると、この自己点検結果の報告が3年に一度の提出でOKになります。知らずに毎年報告していた、という学校も多いかもしれませんね。
メリット3:学校の信頼性向上と募集力の強化
適正校になると、COE交付率が安定している適正校(特にクラスⅠ)は、エージェントから優先的に学生を紹介されやすくなります。また、入管からの「お墨付き」は安心感につながり、学校選びで有利になります。
COE交付の場面では、在籍管理が適正と評価されるため審査がスムーズになり、特に適正校クラスⅠでは高い交付率で安定するため、結果として安定した募集計画・学校経営が可能になります。
適正校判定に影響する意外なケース(落とし穴)
「うちは真面目にやっているから大丈夫」――そう思っていても、思わぬところで評価を下げてしまうケースがあります。ここでは、特に注意すべき「落とし穴」を3つ紹介します。
ここからは運営実績の長い告示校の方々でも知らなかった、というパターンもあるかと思いますので要チェックです。
ケース1:届出遅延でイエローカード
出入国管理及び難民認定法 第19条の17では、中長期在留者の受入れ機関に対し、受入れ開始と終了の報告義務を課しています。
特に「留学」の在留資格を持つ留学生を受け入れる場合は、以下のタイミングで14日以内の届出が必要です。
- 受入れ開始:入学や転学
- 受入れ終了:卒業、退学、除籍
- 在籍状況報告:毎年5月1日・11月1日時点の在籍状況
この報告がしっかりとできていないと、入管より指導を受ける場合があります。これは、受入れ期が年4回ある学校では毎年4回必要なほか、転学生の受入れなどを行った際にも14日以内に届出をしなければなりません。
適正校判定においては、段階的に影響を受けます。
届出遅延で1回指導を受ける → 適正校Ⅰの基準を満たせなくなる
★2回続けて指導を受けると → 通常の適正校の基準も満たせなくなるので要注意です!
ケース2:改善指導書=即マイナス評価
続いて、改善指導を受けたケースです。告示基準を満たさない状態が続くと、入管から改善を求める「指導書」が発行されます。これを受けると適正校判定においてマイナス評価となります。
入管庁HPには「在籍管理上の是正すべき点について書面による指導を受けた場合」と記載されていますが、実際には告示基準を根拠としたすべての指導が該当します。
具体例:
- 明らかな違反例
- 学生数が定員を上回っているなど
- 見落としがちな例
- 学則・教育課程の変更届の遅延
- 教員体制の変更届の遅延など
クラスⅠの場合:指導書が1回でも発行されると、その時点で基準を満たせなくなります。
一度の発行で即マイナス評価となるため、細心の注意が必要です。
ケース3:卒業・退学していても油断は禁物
3つ目のケースは、問題在籍者が思わぬタイミングで加算されてしまうケースです。一見自校での落ち度がないように見えてもカウントされてしまう場合がありますので、しっかり確認しておきましょう。
具体的には、卒業や退学した学生が、その後の進学先(専門学校や大学など)で問題を起こした場合などです。
この扱いは、受入れ終了報告の有無によって決まります。
対象となる場面
- 卒業、退学などで在籍が終了
- 受入れ終了の報告が未提出のまま学生が進路先で不祥事や在留資格更新不備を起こした場合
- 在留資格更新ができなかった、在籍資格違反があった等の事案
本来なら、進路先の学校で問題在籍者が1としてカウントされますが、受入れ終了の報告をしていない場合、0.5ずつを按分する形となる場合があります。
新規校と既存校、それぞれの注意点
最後に、学校の状況別に注意すべき点をまとめます。
【新規校の場合】初年度の運営こそが勝負
新規開設校は初年度、在籍実績がないため適正校判定の対象外(「新規・再開校」扱い)になります。
しかし「2年目から頑張ればいい」という考えは危険です。
翌年の判定は初年度の運営実績で評価されるため、開校時から以下の体制を整えることが重要です。
- 出席管理
- 各種届出
- 学生指導
初年からしっかりと管理体制を構築し、次年度以降に備えることが重要です。
【既存校の場合】「慣れ」と「体制の崩れ」に注意
長年、適正校として認められてきた学校ほど注意が必要です。「これまで問題なかったから」という慢心が、評価ダウンにつながりやすくなります。
特に注意すべきは次の点です。
- 担当職員の異動・退職:引継ぎ不足による報告漏れやミス
- 報告体制の形骸化:出席率チェックや学生面談記録が甘くなり、適切な指導を行っていた証明ができない
対策として、業務フローの定期見直し、マニュアル整備、ダブルチェック体制の構築が不可欠です。
まとめ:「適正校」は学校経営の生命線
「適正校」とは、単なるラベルや肩書きではありません。それは、日々の業務効率、教育機関としての信頼性、そして学生募集力に直結する、学校経営の根幹をなす重要な指標です。
今回の記事でご紹介したポイントを参考に、ぜひ一度、貴校の在籍管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、学校の未来を大きく変えるかもしれません。
日本語学校の設立を本格的に検討されている方へ
認定制度に即した設立準備や申請の流れについて、
専門コンサルタントが無料でアドバイスいたします。