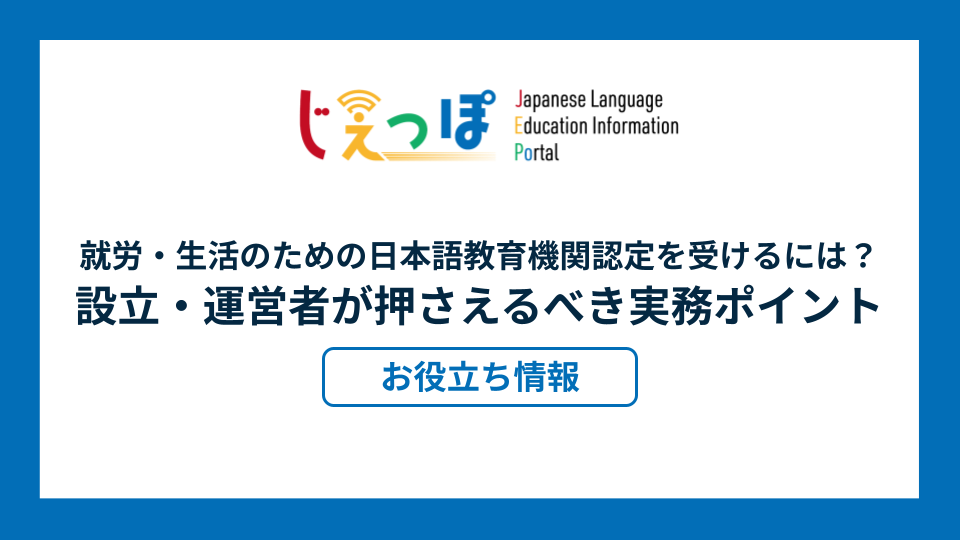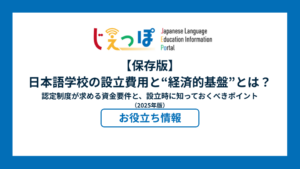2024年4月に施行された「日本語教育機関認定法」により、認定日本語教育機関・登録日本語教員の制度が本格始動して1年半。審査と情報公開の運用が走り出しました。
特に就労・生活のための課程は、留学課程とは準備の勘所が異なります。初年度の審査では認定や不認定が公表され、次のラウンドでは就労課程の申請も始まっています。
本記事では、設立・運営者が押さえるべき要件と準備手順を、最新動向と実務の視点で整理します。
認定制度とは?課程ごとに定められた目的
2024年4月に施行された「日本語教育機関認定制度」では、提供する教育課程ごとに審査が行われます。制度開始からすでに1年半が経過し、初回の認定結果も公表されました。各課程には次のように明確な目的が定められています。
- 留学のための課程
大学や専門学校への進学、日本での就職などを目指して入国した学習者に対し、目的達成に必要な水準の日本語力を習得させることを目的とします。 - 就労のための課程
日本で働く外国人に対し、職場で必要となる日本語力を身につけることを目的とします。 - 生活のための課程
日本に居住する外国人に対し、日常生活に必要な日本語力を習得させることを目的とします。
認定を受けることで、機関は「この課程に応じた教育を適正に提供できる」と国に認められ、情報は文部科学省から公表されます。
認定を受けるための要件:就労・生活課程に特化したポイント
就労・生活課程の認定を受けるためには、一般的な基盤や教員配置だけでなく、就労・生活の目的に即した体制整備が特に重視されます。
- 設置者の経済的基盤
短期で終わらず、地域や企業と継続的に連携して教育を提供できる安定経営が求められます。 - 目的に合ったカリキュラム
就労課程では「業務遂行に必要な日本語」や「職場での安全・ルール理解」、生活課程では「役所での手続き・医療・子育て」など、実践的な場面を想定したカリキュラムが不可欠です。 - 質の高い教員
登録日本語教員資格を持つ教員を確保するだけでなく、職場コミュニケーションや生活支援に関する知見を持つ人材を配置できるかが評価のポイントになります。 - 施設・設備の整備
働きながら・生活しながら学ぶ受講者も多いため、夜間・週末対応、オンライン授業環境など柔軟な学習環境を整えることが望まれます。 - 企業・自治体との連携
就労課程では受け入れ企業との研修や実務連携、生活課程では自治体・NPO・医療機関などとの協力体制が重視されます。協定書や委託契約の有無が審査上の裏付けになります。 - 情報公開と自己評価体制
学習成果や支援体制を可視化し、企業・自治体・地域社会にもわかる形で公開・評価することが求められます。
特によく聞かれる質問:FAQ
就労・生活課程の認定を検討する際に、多くの学校や団体が直面するのが「よくある疑問」です。ここからは、制度運用に関する代表的な質問とその回答を整理します。
Q1. 企業や自治体との連携は、どんな形が実績として認められるの?
認定申請でよく問われるのが「どの程度の連携実績が必要か」という点です。
A: 企業から委託を受けて日本語研修を提供したり、自治体の委託事業に参画したりするケースが代表例です。協定書や契約書など、連携を示すエビデンスを提出できれば、実績として評価されます。たとえば「外国にルーツを持つ子どもへの支援事業」に参画した例も含まれます。
Q2. 就労課程・生活課程で学ぶ人に、在留資格の制限はある?
「技能実習だけ?」「特定技能も?」と混乱しがちですが…
A: 在留資格で制限はかかりません。課程の目的(就労か生活か)に基づいて設定され、留学生・技能実習・特定技能・永住者など、さまざまな資格を持つ学習者が対象になります。
Q3. 教員数はどのように計算するの?
「専任を何人置けばいいの?」という質問も多く寄せられます。
A: 就労のための課程・生活のための課程ともに授業の3/4はオンラインで実施することができるため、基準は「同時に授業を受ける学習者数」の最大値。最も多い時間帯のクラス数を基に算定するのが原則です。
Q4. 認定を受けないと、何が不利になるの?
制度が始まってから「認定を取らなくても学校は運営できるのでは?」という声もあります。
A: 認定を受けなくても運営自体は可能です。文部科学省では、「文部科学省認定」のブランドは大きく、学習者や企業からの信頼、広報活動での優位性、自治体との連携などで有利に働く、とされています。
Q5. 企業にとって、認定機関に依頼するメリットは?
A: 「質の担保」が最大のメリットです。外国人社員に必要な日本語力を計画的に伸ばせるため、業務の円滑化や人材育成の効果が期待できます。企業側の安心材料としても評価されやすい可能性があります。
Q6. 技能実習の入国後講習だけを行っている団体も、認定を受ける必要がある?
A: 技能実習制度自体が「育成就労制度」へ移行する流れの中にあります。取扱いは入管庁・関係省庁で検討が続いており、正式な対応は制度改正のタイミングで示される予定です。
Q7. 短期滞在者を受け入れる場合、生活課程に含まれるの?
A: 原則は「一定期間日本に居住している生活者」が想定対象です。ただし要件を満たす短期課程であれば、認定対象になる可能性はあります。
まとめ:認定取得で、質の高い日本語教育を
現時点で 生活のための課程では認定機関はゼロ という状況です。また、就労のための課程も、認定されている機関は極めて少数です。
背景には、検討が続く 育成就労制度 との兼ね合いがあり、「入国後講習を実施している機関が認定を取得する必要があるのか」といった点を注視する声も少なくありません。
したがって設立・運営を検討する側としては、
- 目先の準備は怠らず進めつつ
- 最新の公表データや省庁発表を逐次チェックし
- 制度改正や新方針が示された際に即応できる体制を整えておく
ことが欠かせません。
認定制度はまだ流動的な段階にあります。理解と情報収集を継続的に行い、制度の決定・周知が行われた際にスムーズな意思決定ができるよう、早めの準備を進めておくことをお勧めします。
次回申請に向けて、お悩みはありませんか?
- コースの組み立て方が分からない
- カリキュラムが基準を満たしているか不安
- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい
実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。