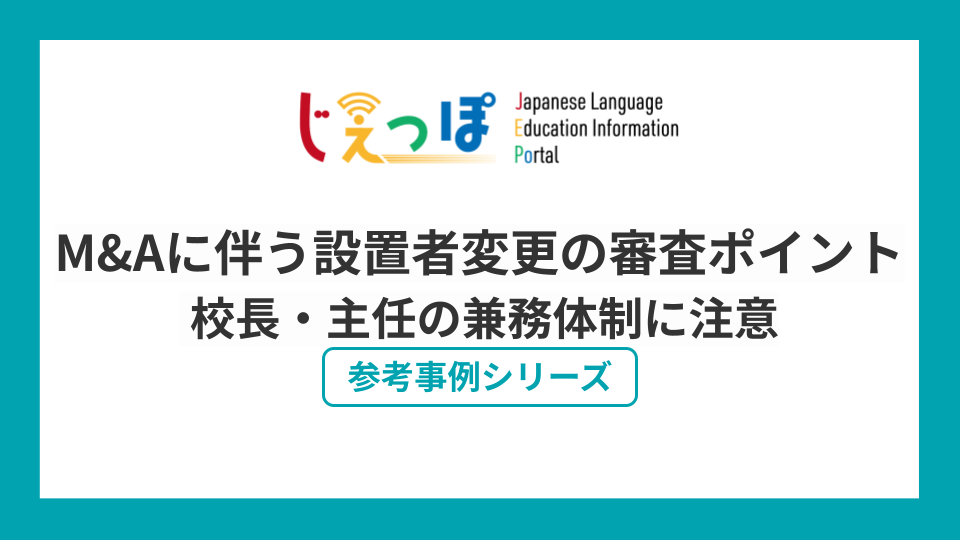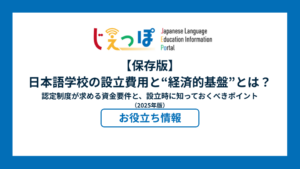近年、設置者変更や事業承継(M&A)を伴う日本語学校の再開が増えています。
コロナ禍による休校や設置者の高齢化をきっかけに、新しい事業者が学校を引き継ぐケースが少なくありません。
こうした設置者変更は、旧制度(告示校)から新制度(認定校)への移行期に特有の動きです。
経過措置の期間内、すなわち2029年3月末までしか行うことができず、その後は「新設」として認定申請を行う必要があります。
今回は、この移行期に実際に行われた設置者変更の事例をもとに、校長と主任の兼務体制が不適格と判断された経緯を紹介します。
※本記事は、当社が関与した事例等を基に一般化・再構成した内容を含みます。特定の学校や審査結果を示すものではありません。
事例の背景 ― M&Aに伴う設置者変更の申請
今回取り上げるのは、事業譲渡(M&A)に伴い設置者変更が行われた日本語学校の事例です。
もともと老舗の学校で、長年にわたり留学生を受け入れてきましたが、コロナ禍の影響で学生数が減少し、運営を継続することが難しくなっていました。
そこで、技能実習生の研修事業などを行う企業グループが学校の事業を引き継ぎ、新たな法人を設置者として登録する必要が生じました。この際に実施されたのが、設置者変更の申請手続きです。
申請では、学校運営体制の再構築や教職員の再配置に加え、人事・経理・文書管理などの内部統制を新設置者側に引き継ぐ必要がありました。
また、留学生の在留資格が一部有効な状態であったため、不法残留などによる非適正校リスクを回避するための確認も並行して行われました。
当時はまだ、M&Aを通じて学校事業を承継するケースが少なく、設置者変更の運用面でも整理が進んでいなかった時期にあたります。このような「移行期特有の不確実性」の中で行われた申請でした。
不適格とされた理由 ― 校長と主任の兼務体制
この申請は、法務省出入国在留管理庁(以下、入管)による「告示日本語教育機関」の設置者変更審査のもとで行われました。
審査の結果、不適格と判断された主な理由は、校長と主任教員の兼務です。
設置者変更後の新体制では、前任校で主任教員として勤務していた教員を中心に再編を行い、経験を踏まえて校長職を兼務させる体制として申請が行われました。
しかし、入管はこの兼務体制を認めず、「校長と主任教員はそれぞれ独立した職務として配置する必要がある」と判断しました。
校長は学校運営の最終責任者であり、主任教員は教育課程の編成・授業運営を統括する立場にあるため、両者を兼ねることで職務の独立性と監督機能が損なわれると見なされたものです。
また、面談時の説明内容と提出書類の整合性にも課題がありました。
書類上では役職分担が明記されていたものの、面談では主任教員本人が「授業や担任業務を中心に担当する」と説明しており、実態としては校長としての職務を十分に果たしていないと判断されました。
このように、形式上の配置と実態の乖離が見られる場合、審査では体制全体の信頼性が低下すると捉えられます。
経験年数や肩書きだけでなく、「どの役職がどの範囲の判断を行うのか」を明確に示すことが求められます。
再申請での改善と通過のポイント
不適格の結果を受け、学校側は校長・主任・事務統括の三役を明確に分離した体制で再申請を行いました。
兼務を解消し、校長職には他校での管理経験を持つ人物を新たに採用。
主任教員は教育課程や授業運営に専念できるよう、役割と職務範囲を明文化しました。
申請時には、三役それぞれの職務分担と意思決定の流れを組織図と決裁フローで明示。
加えて、日常の会議体制・報告経路・教職員間の情報共有方法など、実際の運営に即した体制説明資料を添付しました。
面談においても、三役全員がそれぞれの立場から回答できるよう準備を行い、校長は学校全体の運営方針、主任教員は教育課程の設計と授業管理、事務統括は留学生管理や届出手続きの運用を中心に説明を行いました。
これにより、組織としての独立性と相互牽制が機能していることを示すことができました。
結果として、再申請は「適格」と判断され、設置者変更が承認されました。
この事例では、体制図の明確化や三役間の職務定義といった書面上の整備に加えて、面談での整合性確認まで含めた一貫性が通過の決め手となりました。
事例から見える留意点 ― 設置者変更における審査の本質
設置者変更は、書類上は法人の交代に見えますが、審査の実態は「新設に準じた運営体制の確認」です。
入管は、旧設置者からの引継ぎ内容だけでなく、新設置者が学校運営をどのように理解し、どの程度主体的に運営できるかを慎重に見ています。
特に、校長・主任教員・事務統括の三役がそれぞれの役割を果たせるか、また意思決定の流れが明確に整理されているかが重要な判断軸となります。
「兼務で成り立つか」ではなく、「独立した職務体系として説明できるか」が問われる点に留意が必要です。
さらに、面談では書類に記載された体制と実際の理解が一致しているかが重視されます。
書面と発言の間にずれがあると、体制そのものの信頼性が損なわれるため、各役職者が自らの職務を理解し、具体的に説明できるよう準備しておくことが不可欠です。
まとめ
設置者変更は、旧制度における最後の「運営体制の再構築の機会」といえます。
この制度自体は2029年3月で終わりますが、審査で問われるのは「体制をどこまで主体的に説明できるか」という、認定制度にも通じる視点です。
形式的な承継ではなく、実質的に持続可能な運営体制を築く姿勢こそが、これからの認定申請・運営改善の土台となります。
移行期にある今だからこそ、審査を“制度理解の終点”ではなく、“次の制度への入口”として捉えることが重要です。