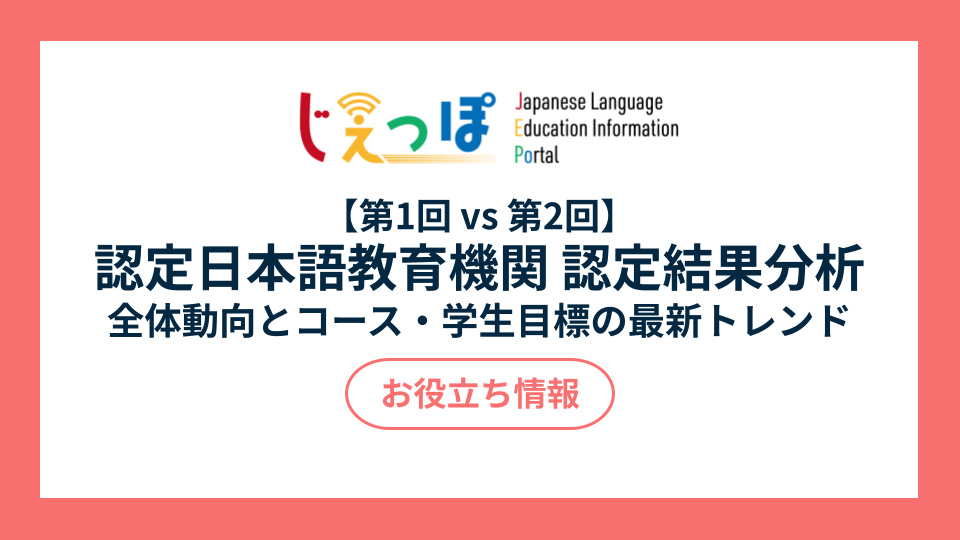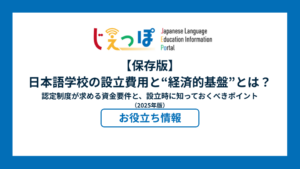2024年4月から「日本語教育機関認定法」が施行され、「認定日本語教育機関」制度が本格的にスタートしました。
すでに2回の認定結果が公表され、今後の申請を検討されている学校様にとっては、その動向は非常に気になるところかと思います。
本記事(第1部)では、令和6年度に行われた認定結果の第1回と第2回のデータを徹底比較・分析。まずは認定率や申請機関の傾向といった全体像と、そこから見えてきた認定コースの特色や学生が目指す目標のトレンドをわかりやすく解説します。
最新の動向を把握し、今後の申請戦略やコース設計を考える上での基礎情報として、ぜひお役立てください。
第2部では、審査で具体的にどのような点が重視されているのかを詳しく解説します。

認定結果 第1回 vs 第2回:数字で見る変化
まずは、第1回(R6.10.30認定)と第2回(R7.3.31認定)の結果を比較し、全体の傾向をつかみましょう。
申請・認定状況:認定率は上昇も、取下げ増加で準備の重要性増す
| 項目 | 第1回 (R6.10.30認定) | 第2回 (R7.3.31認定) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 申請機関数 | 72機関 | 48機関 | 減少 |
| 認定機関数 | 22機関 | 19機関 | やや減少 |
| 不認定機関数 | 3機関 | 0機関 | 減少 (ゼロ) |
| 審査中に取下げた機関数 | 36機関 | 29機関 | やや減少 |
| 認定率 (全申請機関数ベース) | 約30.6% (22/72) | 約39.6% (19/48) | 上昇 |
| 取下げ率 | 50.0% (36/72) | 約60.4% (29/48) | 上昇 |
まず注目すべきは、第1回から第2回にかけて、申請機関数自体が72機関から48機関へと減少した点です。
この背景には、制度開始初期の様子見期間が終わり、より現実的な判断をする機関が増えたことや、認定基準のハードルの高さを認識し、準備が整うまで申請を見送る機関が増えた可能性が考えられます。
さらに、文部科学省は申請前に「事前相談」 の機会を設けています。この事前相談を活用した結果、申請要件を満たすことが現時点では難しい、あるいは準備に更なる時間が必要だと判断し、正式な申請には至らなかった機関も一定数存在する可能性があります。
つまり、申請数の減少は、単に意欲が減退したというよりは、より現実的な判断や準備段階でのスクリーニングが影響しているとも考えられます。
第2回では、認定率が約39.6% という結果になりました。これは、申請機関側が基準への理解を深め、より質の高い準備を行うようになったことに加え、申請に至る機関が絞られたことや事前相談の効果により、審査に進む機関の準備レベルがある程度向上した結果とも推測できます。
しかしながら、申請を取り下げた機関の割合は50%から60%超へと増加しており、審査プロセスに進んだとしても、その要求水準は依然として高く、準備不足は取下げにつながる可能性が高いことを示唆しています。
これらの状況を総合すると、「認定のハードルは高く、安易な申請は避けるべきであること。そして、十分な準備と、必要であれば事前相談の活用も視野に入れ、計画的に申請に臨むことの重要性がますます高まっている」と言えるでしょう。
認定申請、気になっていませんか?
「うちも申請すべきなのかな…」
「どのコースで申請すればいいか分からない」
そんなお悩みは、制度と実務に詳しいスタッフが無料でご相談を承ります。
(初回ご相談無料・Zoom対応OK)
申請・認定機関の傾向:多様な設置者、「留学」中心に「就労」も
課程分野:
両回ともに申請・認定の中心は「留学」課程です。これは認定制度が在留資格「留学」と直結しているため当然の流れです。
注目すべきは、第2回で「就労」課程が2機関認定された点です(第1回は0機関)。
これは、今後導入が予定されている「育成就労制度」において、就労する外国人の日本語能力向上のための講習を、認定日本語教育機関の「就労」課程が担うことが有力視されている動きと関連している可能性があります。
機関種別:
申請機関の内訳を見ると、「法務省告示機関」からの移行組と、新規日本語学校への参入を示す「その他(主に民間企業や各種法人等が設置する機関、専門学校等)」からの申請に大別できます。
これは、多様なバックグラウンドを持つ事業者が日本語教育分野に積極的に参入し、認定を受けていることを示しています。引き続き新規参入も活発であると言えます。
認定コースの特色と学生の目標:進学主流も、目的特化と到達目標の明確化が鍵
認定された機関のコース内容や留意事項を見ていくと、どのようなコース設計や学生の目標設定が求められているかのヒントが見えてきます。
主流は依然「進学」目的:
認定されたコースの多くは、「進学2年課程」「大学進学コース」「専門学校進学課程」といった名称で、日本の大学、大学院、専門学校への進学を主目的としています。
コース期間は「2年」「1年6か月」が多く、入学時のレベルに応じて段階的に日本語能力を引き上げる標準的なモデルが主流です。
「就職」目的コースの登場と特色化:
前述の通り、「就労」分野での認定が出てきました。
第1回の認定機関の中にも、「就職2年課程」や「キャリア形成実用日本語学科(就職準備コース)」といった名称のコースが見られ、「留学」ビザで学びながらも、卒業後の日本での就職を明確に視野に入れたコース設計が増えています。
これらのコースでは、一般的な日本語能力に加え、ビジネス日本語や特定の業界(例:留意事項にあった介護分野など)で求められるコミュニケーション能力の育成が目標とされています。
専門分野特化・地域連携の動き:
「美術系進学コース」「就職のための進学(介護分野等)」のように、特定の専門分野への進学・就職に特化したコースも見られます。これらのコースでは、専門分野で必要な語彙や表現の習得が重要視されます(留意事項でも指摘あり)。
地方の機関では、地域社会との連携(例:大崎市立)や、地域の産業(例:嬉野・霧島の就職課程)との結びつきを意識したコース設計も見られます。
到達目標レベルの明確化と測定可能性:
認定申請では、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)のレベル(例:B1、B2、C1)が到達目標として設定されます。
留意事項では、「目標レベルとカリキュラムの整合性」「入学時のレベル設定の妥当性(例:1年半でB2を目指すなら入学時B1が必要など)」「目標達成度を測る評価方法の具体性」などが指摘されており、単に目標レベルを掲げるだけでなく、それを達成するための具体的な道筋と、客観的に測定可能な評価方法の設計が求められています。
JLPT合格を目標に含めるコースもありますが、それが主目的化したり、評価の唯一の基準になったりしないよう、あくまで能力を測る指標の一つとして位置づける必要があります(留意事項でも外部試験の位置づけに関する指摘あり)。
「日本文化理解」「日本社会探求」など多様な目標設定も:
単なる進学・就職だけでなく、「日本理解のための日本語課程」「日本社会探求コース」「日本語・文化2年課程」といった、より広い視野での異文化理解や社会参加を目標とするコースも見られます。
これらのコースでは、知識習得だけでなく、主体的な探求活動や成果発表(例:修了制作)などが評価に取り入れられる傾向があります。
総じて、進学目的が主流であるものの、就職や特定の専門分野への対応、地域との連携など、コースの目的・目標は多様化しています。
どのような目的であれ、その達成に必要な日本語能力(参照枠レベルで示されることが多い)を明確にし、具体的なカリキュラムと評価方法を設計・運用することが、認定を得るための重要なポイントと言えます。
【まとめ】認定結果から見る全体像とコース・目標のトレンド
今回は、認定日本語教育機関の第1回・第2回認定結果を比較し、全体的な傾向とコース・学生目標のトレンドを分析しました。
- 認定状況: 審査通過機関の認定率はやや上昇したが、申請取下げ率も増加。準備の質と計画性がより重要に。
- 申請機関: 多様な設置者(特に民間企業等)が参入。「留学」課程中心に、「就労」課程も認定開始。
- コース・目標: 「進学」目的が主流だが、「就職」目的や専門分野特化、地域連携型も増加。目標達成に必要な到達レベル(CEFR等)を明確化し、具体的なカリキュラムと評価方法を設計・運用することが鍵。
これらの全体像とトレンドを踏まえ、次に気になるのは「審査では具体的にどのような点が厳しく見られているのか?」 という点でしょう。
次回の記事【第2部:審査の重要ポイント解説と今後の対策】では、認定・不認定の理由や留意事項を項目別に深掘りし、合格に向けた具体的なポイントとアクションプランを徹底解説します。ぜひ続けてご覧ください。

次回申請に向けて、お悩みはありませんか?
- コースの組み立て方が分からない
- カリキュラムが基準を満たしているか不安
- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい
実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。