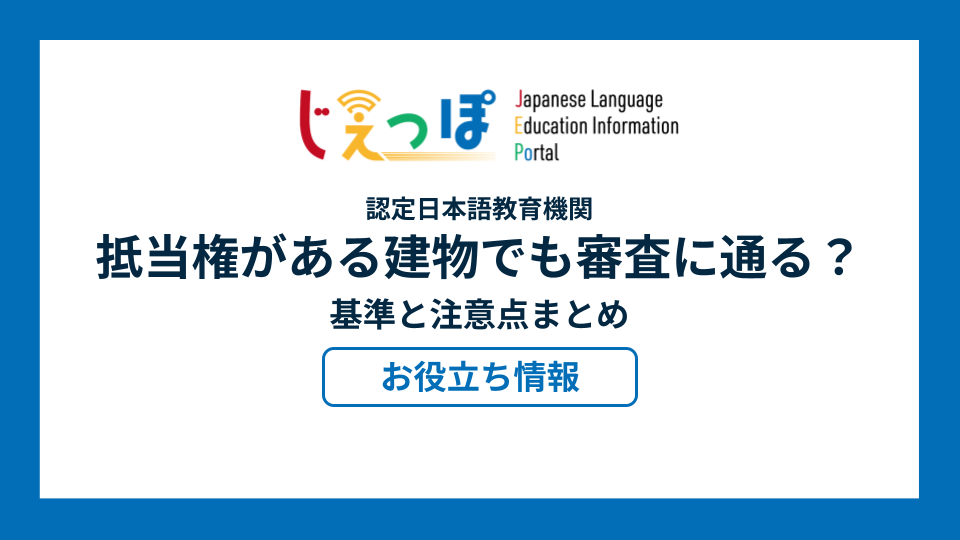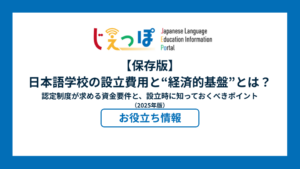日本語教育機関の皆さま、そしてこれから認定校を目指そうと考えている皆さま、こんにちは!
日本語教育の質の確保と向上を目指す「認定日本語教育機関制度」が始まり、多くの日本語学校が認定取得に向けて準備を進めているかと思います。
そんな中、よく耳にするご質問の一つに「学校の建物や土地に『抵当権』が設定されている場合でも、認定を受けることはできるのでしょうか?」というものがあります。
学校を運営していく上で、校舎や土地は重要な資産であり、資金調達のために抵当権を設定しているケースも少なくありません。これが認定の際に不利になるのではないか、と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、認定日本語教育機関の基準や関連する告示、さらには実際に認定を受けた学校のデータをもとに、この疑問について詳しく解説していきます!
認定校として日本語学校を設立したい方へ
認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、
無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。
対象:設立検討中/制度に不安がある方
抵当権とは?学校運営への潜在リスク
まず、抵当権について簡単に確認しましょう。
抵当権とは、借金の担保として不動産に設定される権利のことです。もし借金の返済ができなくなると、担保である不動産が差し押さえられたり、競売にかけられたりする可能性があります。
学校運営の観点では、校舎という重要な施設を失うリスクがあるため、「安定した継続運営」に支障をきたす可能性が懸念されることがあります。だからこそ、「抵当権があると不利になるのでは?」と心配されるのも無理はありません。
認定基準をチェック!施設の所有に関するルール
では、認定日本語教育機関の基準では、施設の所有についてどのように定められているのでしょうか?
認定基準の第三章「施設及び設備」を見てみましょう。特に第十二条(校地)と第十三条(校舎)の第四項には、施設の所有に関する規定があります。
- 第十二条第二項(校地):認定日本語教育機関は、校地を設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。
- 第十三条第四項(校舎):認定日本語教育機関の校舎は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。
ここにはっきりと「設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないもの」が原則と書かれていますね。「負担附き」とは、まさに抵当権などが設定されている状態を指します。
原則としては、抵当権がついていないクリーンな状態が求められている、ということです。
原則は自己所有・負担なし。でも例外があるんです!
先ほどの基準には「ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない」という重要な一文がありました。
つまり、原則は「自己所有かつ負担なし」ですが、例外的に「自己所有・負担なしと同等と認められる場合」であれば、抵当権などが設定されていても認定を受ける可能性がある、ということです。
では、「自己所有・負担なしと同等と認められる場合」とは、具体的にどのようなケースを指すのでしょうか?これは、文部科学省が出している「必要な告示を定める件」という別の告示で詳しく定められています。
詳しく定められた「自己所有と同等」のケース
第二条(校地を自己所有と同等と認める場合)と第三条(校舎を自己所有と同等と認める場合)には、いくつかのケースが列挙されています。その中でも、抵当権などの「負担附き」の状態に関する重要な規定が第一号にあります。
【告示第二条第一号・第三条第一号の要点】
- 校地または校舎が設置者の自己所有であり、かつ、負担附きである場合。
- ただし、その負担附きであることに「やむを得ない事情」があること。
- そして、その負担が設置者の資産状況等から見て、校地や校舎を「長期にわたり使用する上で支障がなく」、さらに「当該認定日本語教育機関を運営することに支障がないことが確実であると認められる」こと。
ここでのポイントは、
- 「やむを得ない事情」があるか
- 長期使用や運営に支障がないことが「確実」か
の2点です。
「やむを得ない事情」とは具体的に何を指すのでしょうか?これもFAQで解説されています。
【FAQから読み解く「やむを得ない事情」】
FAQのQ2-6-4によると、「やむを得ない事情」の例として挙げられているのは、校地や校舎、またはそれを取得するための資金をすぐに準備できず、設置者自身が借入金によって校地や校舎を取得した場合で、その借入れを保証するために抵当権などが付くケースです。
そして、この場合、借入金の返済計画が実現可能であり、近い将来(例えば、認定後最初の修業期間の終期まで等、具体的な時期の明示はないものの、早期に負担がなくなる見込みがあること)には負担がなくなる必要がある、とされています。
さらに重要なのは、新規の認定申請時においては、校地や校舎の「取得」に関わる借入れ以外の目的で設定された抵当権は原則として認められないという点です。(FAQ Q2-6-4参照)
一方で、認定を受けた後であれば、教育の質の充実や自然災害対応など、認定日本語教育機関のためにやむを得ない目的で必要になった資金を借り入れる際に、運営に支障のない範囲で抵当権を設定することは可能となる場合があります。(FAQ Q2-6-5参照)
また、令和11年3月31日までの経過措置期間中は、既存の法務省告示機関などが認定を受ける場合に限り、認定申請時であっても、校舎等の「取得」以外の目的で設定された抵当権についても、審査の結果認められる場合がある、とされています。(FAQ Q2-6-6参照)
まとめると、抵当権が付いている場合でも、それが校地・校舎の取得に関する借入金に伴うもので、「やむを得ない事情」があり、かつ返済計画がしっかりしていて、学校運営に支障がないことが確実に説明できれば、認定の可能性はある、ということになります。特に新規設立校の場合は、取得資金目的の借入れに伴うものに限定される傾向があります。
実例紹介!抵当権付きでも認定された学校は存在する
「でも、実際どうなの?」と思われる方もいるかもしれません。結論から言うと、抵当権が設定された状態でも日本語教育機関として認定を受けている学校は、確かに存在します。
2024年〜2025年にかけて認定された約40校のデータを調査した結果、少なくとも10校以上が、土地または建物に抵当権や根抵当権が設定された状態で認定を受けています。これは全体の約4分の1にあたります。
いくつかの例を見てみましょう。
- 実例A(既存校・関東):
- 抵当権設定額:約5,000万円
- 設定時期:認定申請より前
- 所有者:設置者(株式会社)
- 長年運営している学校で、以前の借入に伴う抵当権がありましたが、認定されています。
- 実例B(新規開設校・関西圏):
- 抵当権設定額:約2億円
- 設定時期:認定申請の直前
- 所有者:設置者(株式会社)
- 新規校舎の取得資金として多額の借り入れを行い、申請直前に抵当権を設定しましたが、認定されています。
これらの実例は、「抵当権がある=認定不可」ではないことを明確に示しています。設置者が不動産の所有者であり、その上で学校の運営権限や経営の安定性を説明できることが重要であると言えます。
認定審査での注意点と実務対応
抵当権があっても認定は可能ですが、審査で確認されるポイントや、準備しておくべき事項があります。
- 不動産登記簿の提出: 申請時には必ず校舎・土地の不動産登記簿を提出します。ここに抵当権の有無は記載されるため、審査側は認識します。正直に提出し、必要に応じて説明できるようにしておきましょう。
- 所有者≠設置者の場合: もし校舎の所有者が設置者と異なる場合(例:理事長個人所有など)、設置者が校舎を「長期にわたって安定的に使用できる」ことを証明する賃貸借契約書や使用貸借契約書が必要です。契約期間が十分であることなどが確認されます。
- 長期安定運営の説明: 最も重要です。抵当権がある借入金について、返済計画が具体的かつ現実的であること、そして学校全体の経営状況が健全であり、借入金の返済が教育活動に支障をきたさないことを、自己点検書などでしっかりと説明する必要があります。学校の収支計画なども説得力のある資料となります。
- 補足資料の準備: 場合によっては、融資証明書や詳細な返済計画、資金繰り表など、抵当権設定の背景や返済能力を示す追加資料の提出を求められることもあります。スムーズに対応できるよう、事前に準備しておくと安心です。
まとめ:抵当権は「NG」ではない、重要なのは「説明」
今回の内容をまとめます。
- 校舎に抵当権が設定されていても、日本語教育機関の認定取得は可能です。多くの実例があります。
- 認定審査では、抵当権の有無そのものより、それが学校の「安定した継続運営」を脅かさないかどうかが重視されます。
- 大切なのは、設置者が校舎を使用する安定性(所有または長期契約)と、学校全体の経営状況の健全性を、審査側に具体的に説明できることです。
- 不動産登記簿や必要な契約書の提出に加え、自己点検書等で返済計画や経営状況について丁寧な説明を行いましょう。
抵当権があることで認定申請に不安を感じる必要はありません。適切な資料準備と、学校の安定性をしっかりと説明する姿勢が、認定への鍵となります。
もし、ご自身の状況で不安な点がある場合は、日本語学校の認定に詳しい専門家やコンサルタントに相談してみるのも良いでしょう。
この記事が、皆さんの認定申請準備の一助となれば幸いです。
日本語学校の設立を本格的に検討されている方へ
認定制度に即した設立準備や申請の流れについて、
専門コンサルタントが無料でアドバイスいたします。