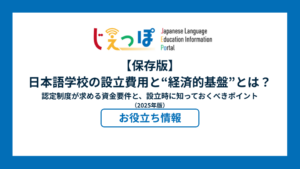日本語学校のうち、留学ビザによって滞在する留学生を受け入れる学校は「告示校」と呼ばれます。法務省によって、その学校名が告示されていたことによるものです。
しかし、2024年4月に施行された「認定法」により、告示校は認定校に完全移行する形となり、現在では新たに告示校として設立される日本語学校は存在しないこととなりました。
なぜ「認定校」が生まれたのか?告示校との違いは何か?ということについて、以下では、告示校から認定校への移行背景と、それぞれの違いを詳しく解説します。
認定校として日本語学校を設立したい方へ
認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、
無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。
対象:設立検討中/制度に不安がある方
告示校とは?
- 法務省による管轄: 告示校は法務省が所管し、入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づいて運営されています。
- 告示基準によって要件が示されている: 告示基準に基づき、外国人留学生が「留学ビザ」を取得する条件を満たした学校として認められています。
- 特徴: 外国人の在留管理に重点を置いた基準による学校管理が特徴です。定期的に在籍者の状況について報告が必要で、それに応じて学校を「適正校」などに分類しています。
在留外国人が増加している傾向にある一方で、教育の質の確保に課題が見られていたことから「認定教育機関」の制度が生まれました。
認定校とは?
- 文部科学省による管轄: 文部科学省が所管する日本語学校で、認定法に基づいた基準を満たす必要があります。
- 認定法などにより要件が示されている: 文部科学省が定める「認定法」「施行規則」「認定基準」「確認すべき事項」「指針」「ガイドライン」などに基づいて審査が行われ、認定を受けます。認定校になった日本語学校は、在留資格「留学」で滞在する外国人を受け入れることができます。
- 特徴: 教育品質の向上などを目的として成立した制度のため、カリキュラムや学生の進路で設定する目標などに特に指針が示されています。
2024年4月の認定法施行時点で告示校である学校は、5年間の移行期間で認定校とならなければなりません。
また、新たに在留資格「留学」で滞在する学生を受け入れる日本語学校を設立しようとする日本語学校は「告示校」ではなく「認定校」としての審査を受けなければなりません。
告示校から認定校への移行の背景
日本語教育においては、これまでさまざまな課題が認識されていました。これらの課題の解決を目的として、「認定法」の整備が行われるようになったのです。
課題:日本語教育の環境整備や教育の質の確保が不十分
告示校として運営されていた日本語学校においては、「日本語総合コース」などのように学習期間の間に進学や就職を決定するといった運営も多く行われていました。
しかし、認定校として学校運営をするにあたっては、「就職コース」「進学コース」など、学生の目的に合わせたコース設計をすることを原則としています。
学習者、自治体、企業等が日本語教育機関選択の際、教育水準等について正確・必要な情報を得ることが困難だったことから、学習者にとって環境を整備すること、教育の質を確保することなどが目指されています。学習者がわかりやすいコース名の設定を推奨することで、よりよい環境整備などが目指されています。
また、学習者やその他の関係者が日本語学校を選ぶ際に、どのような特色があるのかが不透明な状況が続いていました。文部科学省は、認定法の施行と同時に「認定日本語教育機関法ポータル」を新たに作成し、ここで認定を受けた日本語学校の情報を確認できるよう整備を進めています。
課題:専門性を有する日本語教師の質的・量的確保が不十分
これまで告示校で学生に対し授業を行うことができるのは、主に下記の通りでした。
しかし、日本語教育の質の確保をするにあたり、日本語教師に求められる能力の水準も変化しています。認定法では、勤務する教員についてもすべて「登録日本語教員」であることを求めています。
登録日本語教員とは、下記の通りです。
これまでの条件に対して、認定法に基づく「登録日本語教員」ではすべての資格取得パターンで試験の合格が必要になります。
日本語教育の質の確保、また専門性を有する日本語教師の質的・量的確保を目指し、資格制度の整備が行われました。資格制度を通じて、日本語教師の質的向上が目指されています。
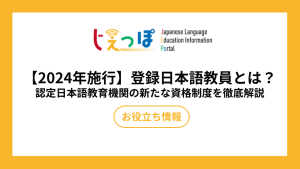
認定校の審査では何が確認されるのか?
これまで、認定校が生まれた背景と、業界の課題について解説してきました。業界の課題を解消するために成立した法律ですので、その設立の要件としてさまざまな確認事項があります。
「認定法」で定められている要件などに関しては、「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」の中でさらに具体的に何が確認されるかが示されています。
確認される事項は多数あります。「設置者(設置する法人)」「学校の体制」「施設・設備」「教育課程(カリキュラム)」「学習・生活支援体制」にわたり確認されますので参考資料に基づいてあらかじめ確認をしておくと安心です。
特に、下記の2点については注意する必要がある項目ですのでこちらでご紹介します。
日本語教育課程に関する事項
日本語教育機関では、学生の日本語能力を段階的に向上させるための体系的なカリキュラムが必要です。
カリキュラムの中では、学生が修了時にどのくらいの日本語能力に到達するのかを示す必要がありますが、認定法に基づく申請においては、コースの中で、B2レベル(日本語教育の参照枠によるレベル)以上に到達するものを1つ以上設置する必要があります。
文部科学省のガイドラインである、「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」を参考にしながら、日本語教育の参照枠に基づいて設計された授業計画を提供しなければなりません。
これまでの日本語能力の測り方ではなく、「何ができるのか」といった視点でのカリキュラム作成が必要になるので、注意が必要です。
教員及び職員の体制に関する事項
認定日本語教育機関で勤務する教員は、新たに国家資格となった「登録日本語教員」でなければなりません。(移行措置期間中は告示校での勤務要件で勤務することができます。)
それにより指導経験や資格を有していることを確認し、さらに学生数に応じて必要な人数の配置が求められます。特に教職員が業界全体で不足しているため、質の高い教職員を確保することが難しくなっています。
また、主任教員については、「教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び技能を有すること」として、他の教員の監督ができるような知識・技能を持っているかどうかが確認されます。
主任教員は要件として、「認定日本語教育機関において、本務等教員として日本語教育に三年以上従事した経験を有すること」とあり、一見すると最低でも3年の本務等教員としての経験があれば満たしているように感じられますが、実際には学校全体の教員をマネジメント、指導していけるような経験・知見などが必要とされます。
具体的には、上述のように「何ができるのか(Cando)」ベースでのカリキュラム作成ができる方を主任教員として採用する必要があるということです。

まとめ
認定校制度の開始に伴い、今後の日本語教育機関はさらに高い水準の教育品質と運営体制を求められるようになりました。
審査の管轄も文部科学省になったことにより、より教育の水準について厳格に審査される制度へと移行しています。カリキュラムの作成経験のある教員を確保し、審査では学校が実現したい教育を体系的に実施できることを証明する必要があります。より丁寧に準備を進めることが、申請を成功させるための鍵となります。
日本語学校設立を検討している方は、認定校基準を理解し、適切な計画を立てることが成功の鍵です。設立や申請に関するご相談は、ぜひ無料相談をご利用ください!
日本語学校の設立を本格的に検討されている方へ
認定制度に即した設立準備や申請の流れについて、
専門コンサルタントが無料でアドバイスいたします。