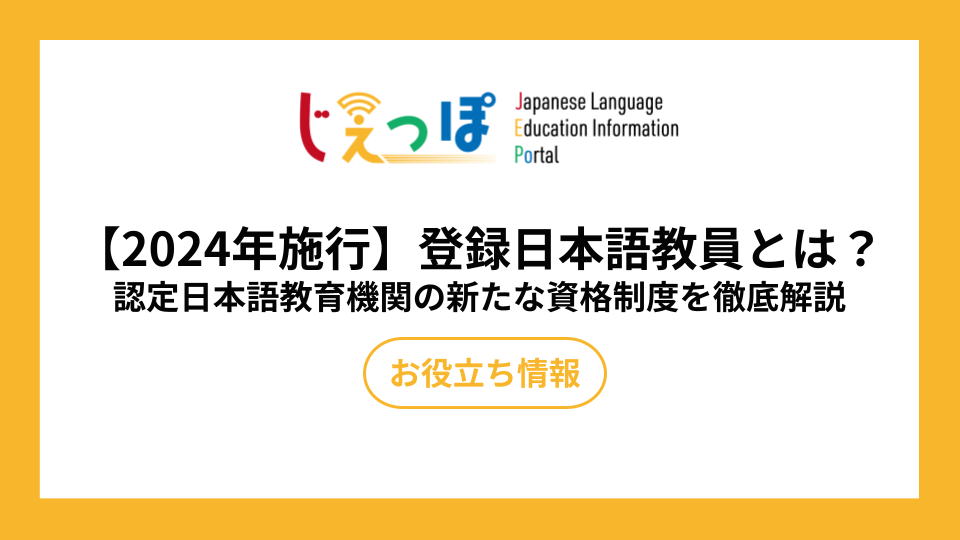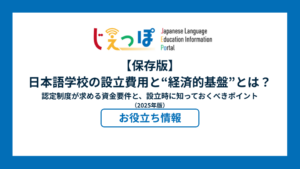日本語教育の現場では、2024年4月から本格施行された「認定法」によって「告示校」が「認定日本語教育機関(認定校)」へ移行する動きが進んでいます。この認定法と同時に大きく注目されるのが、新たに創設された国家資格「登録日本語教員」という制度です。
本記事では、登録日本語教員がどのような資格なのか、取得までの流れや既存の日本語教師との違い、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。認定校を目指すうえで欠かせないポイントをまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
認定校として日本語学校を設立したい方へ
認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、
無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。
対象:設立検討中/制度に不安がある方
登録日本語教員とは?創設背景とポイント
登録日本語教員とは
登録日本語教員とは、2024年4月施行の「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(認定法)」に基づき新設された、国家資格の日本語教師制度です。
これまで日本語教師になるためのルートは「日本語教育能力検定試験の合格」や「420時間の養成講座修了」などがありましたが、新制度では「日本語教員試験への合格」+「実践研修の修了」をもって、文部科学大臣への登録が認められます。
新制度が必要になった背景
- 教育品質の向上: 従来の「告示校」は入管法中心の基準で、在留管理に重きが置かれていた傾向にありましたが、近年は教育の質が課題になっています。新制度ではカリキュラムや教師の質を一層重視する内容となっています。
- 多国籍化への対応: 日本への留学ニーズが高まっており、日本語教師の専門性・指導スキル確保が急務となっています。資格の整備をすることで教師の指導スキル確保を狙っています。
登録日本語教員になるための条件・ステップ
登録日本語教員として認められるには、以下の主なプロセスを踏む必要があります。
- 日本語教員試験に合格
- 2024年11月に第1回が実施された試験で、日本語教育に必要な知識・技能を総合的に判定するものです。基礎試験と応用試験に分かれます。
- 出題範囲や評価基準などが異なるものの、基礎試験は従来の「日本語教育能力検定試験」に近いイメージです。
- 登録日本語教員養成機関を修了した場合には、基礎試験が免除になります。
- 実践研修を修了
- 認定日本語教育機関(または文科省が指定した機関)での実践的な研修を行います。
- 教壇実習や授業準備、模擬授業など、現場力を養成する学習項目が設定されます。
- 従来の420時間の養成講座で実習として実施されていた模擬授業などに該当します。
- 文部科学大臣への登録
- 登録日本語教員としての登録は専用のポータルサイトを通じて行います。
- 試験の合格証や必要に応じた書類の提出が完了すると申請内容の審査が行われます。結果の通知がでると、正式に「登録日本語教員」として認められます。
従来との違い
- 従来は、 「日本語教育能力検定試験合格」「420時間研修」などそれぞれ試験だけ、研修だけのルートとなっていました。
- 新制度となり、養成機関を修了しても応用試験の合格が必要となりました。また、試験ルートを選ぶ際にも実践研修が必須となりました。
既存の日本語教師はどうなる?移行措置と経過措置期間の教員要件
移行措置(経過措置)期間とは
認定法が施行されても、いきなり全員が登録日本語教員の資格を取得しなければならないわけではありません。告示校から認定校へ移行する期間(令和11年度まで)や、既存の日本語教師が資格取得を進めるための移行措置(経過措置)が設けられています。
- 既存教員の場合: 一定の猶予期間内に、所定の要件を満たして登録日本語教員になるための準備を進めれば大丈夫です。
- 学校全体: 認定校へ正式移行するまでの間は、従来の告示要件(例: 日本語教育能力検定試験合格、420時間養成講座修了など)を満たす教員であれば「要件を満たす教員」として扱われます。
ポイント: 経過措置期間中は、告示校での教員要件を満たしていれば可となります。 移行期限以降(最終的には2029年までに)に正式な「登録日本語教員」への移行が求められる可能性があるため、早めの情報収集と準備が重要です。
登録日本語教員制度のメリット・デメリット
登録日本語教員に移行が必要となる新制度は、メリットと同時に一部課題もあります。
メリット
- 教師の質向上・信頼性アップ
- 国家資格となることで、専門性・スキルが担保され、教育水準の底上げが期待できます。
- 国家資格となることで、専門性・スキルが担保され、教育水準の底上げが期待できます。
- 認定校としての評価向上
- 登録教員を多く抱えている学校ほど、学生や、仲介機関、企業からの信頼獲得につながる可能性が高まります。
- 登録教員を多く抱えている学校ほど、学生や、仲介機関、企業からの信頼獲得につながる可能性が高まります。
デメリット
- 人材確保の難易度が上がる
- 新制度によって資格取得ハードルが高まり、一時的に教員不足に陥る恐れがあります。資格取得をあきらめ、日本語教師自体を辞めてしまうという声も一部で聞かれます。
- 新制度によって資格取得ハードルが高まり、一時的に教員不足に陥る恐れがあります。資格取得をあきらめ、日本語教師自体を辞めてしまうという声も一部で聞かれます。
- コスト増
- 教員が資格取得するための研修費用や、採用後の研修支援など、学校側の負担が増える可能性があります。多くの日本語学校では資格取得の補助を負担しています。
- 教員が資格取得するための研修費用や、採用後の研修支援など、学校側の負担が増える可能性があります。多くの日本語学校では資格取得の補助を負担しています。
認定法と登録日本語教員の関係
認定日本語教育機関(認定校)として運営するには、文部科学省の定める基準をクリアしなければなりません。2029年までは全員が登録日本語教員である必要はありませんが、「教員の体制を整え、最終的に全教員が登録日本語教員としての資格を取得すること」は非常に重要な項目です。
- 告示校との大きな違い: かつては告示基準のもと、「日本語教育能力検定試験合格」など既存要件でOKでしたが、認定校では、将来的に登録日本語教員の資格が必須となります。
- カリキュラム設計の視点: 認定校では「Can-do(何ができるようになるか)」を重視した授業計画が求められ、そのためには教員の指導力・設計力が欠かせません。登録日本語教員が増えるほど、スムーズにカリキュラムを作成できるなどメリットもあります。
まとめ|認定校運営・設立に向けてのポイント
日本語教育の世界は、告示校から認定校へという大きな転換期を迎えています。その中で、「登録日本語教員」は学校運営に欠かせない存在となるでしょう。以下のポイントを押さえて、スムーズな移行・設立を目指してください。
- 経過措置期間を正しく理解する
- 施行直後から“完全移行”ではなく、しばらくは告示要件でも可とされる見込みです。
- ただし猶予期間終了後は登録日本語教員必須が本格化するため、早めの準備が肝心となります。
- 施行直後から“完全移行”ではなく、しばらくは告示要件でも可とされる見込みです。
- 早めに資格要件をチェック
- 既存教師・新規採用教員の双方に対し、どのように「試験合格・実践研修」を進めるか計画を立てましょう。
- 移行スケジュールに合わせ、研修費用や休職期間などを考慮しましょう。
- 既存教師・新規採用教員の双方に対し、どのように「試験合格・実践研修」を進めるか計画を立てましょう。
- 認定校審査を見据えた体制づくり
- カリキュラム設計、学生募集、人材配置などトータルで見直し、教育品質を高めていくことが重要です。
- 現在は告示基準での勤務要件を満たしていればOKですが、今後は登録日本語教員の確保状況が審査の大きな要点になる可能性もあるため要注意です。
- カリキュラム設計、学生募集、人材配置などトータルで見直し、教育品質を高めていくことが重要です。
日本語学校の設立を本格的に検討されている方へ
認定制度に即した設立準備や申請の流れについて、
専門コンサルタントが無料でアドバイスいたします。