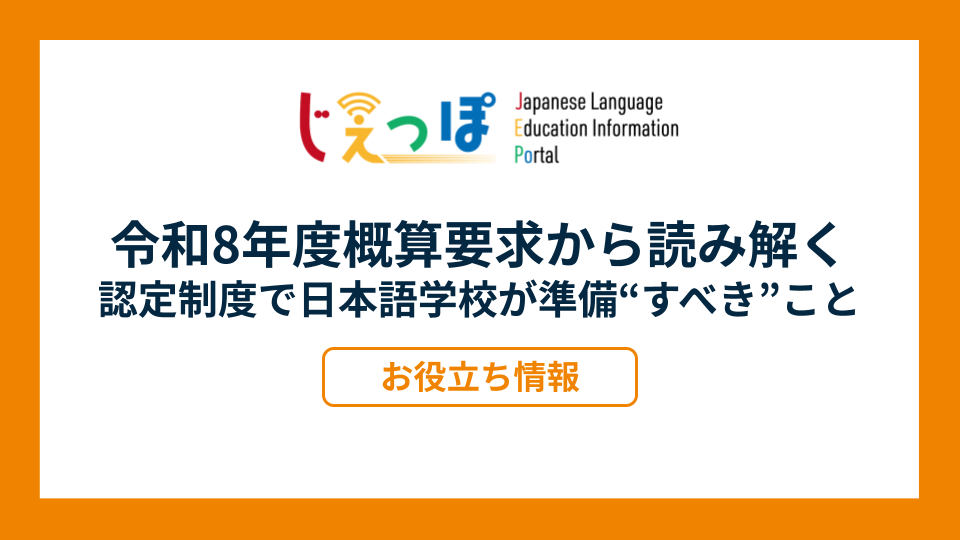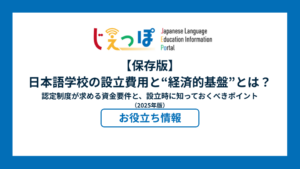教育政策の方向性は、最終的に「予算」によって形を与えられます。
どこに資金が投じられるのかを知ることは、単なる数字の話ではなく、国が教育に何を期待しているかを読み解くことにつながります。
日本語学校を新たに設立しようとする経営者や、すでに学校を運営している方にとっても、この動向を押さえることは今後の戦略を考える上で欠かせません。
本記事では、8月に公開された令和8年度概算要求を令和7年度予算と比較し、教育全体の潮流と日本語教育に関わる重要ポイントを整理していきます。
令和7年度予算の振り返り
令和7年度(2025年度)の文科省予算は総額5.4兆円、教育分野では教員の働き方改革や学校DXが柱となりました。
日本語教育関連では約31億円が計上され、その中心は 「認定制度の円滑な施行準備」。登録日本語教員の試験実施や認定校の情報発信、事務体制整備など、新制度の滑走路を整える内容でした。
令和8年度概算要求では何が変わる?
一方、令和8年度(2026年度)の概算要求は総額6兆599億円と前年比10%増。教育分野では35人学級や教員増員などが掲げられています。
日本語教育関連は 約44億円(前年比+42%) と大幅増。ここでのキーワードは 「制度の本格運用と質の向上」 です。
- 外国人等への日本語教育推進:約22億円
- 外国人児童生徒支援:約22億円
- 新規事業:「日本語教育の参照枠」に基づくカリキュラム開発支援(3.5億円)
- 拡充:認定審査や情報公開など、制度運用の事務経費
つまり、7年度が「滑走路整備」だとすれば、8年度は「質の保証に向けた離陸」の段階。
国が日本語教育を戦略的に強化しようとしている姿勢が、数字にも明確に表れています。
両年度の比較から見える大きな潮流
令和7年度予算と令和8年度概算要求を比較すると、日本語教育政策が運用フェーズに入っていることが分かります。
| 項目 | 令和7年度予算 | 令和8年度概算要求 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 文科省一般会計 | 5兆5,094億円 | 6兆599億円 | 大幅増 |
| 日本語教育関連 | 約31億円 | 約44億円 | 約42%の大幅増 |
| 政策の重点 | 認定法の施行準備 | 認定制度の本格運用と質の向上 | 「準備」から「実践・質保証」へ |
認定制度が運用フェーズに入ることで、国が定めた基準を満たす質の高い教育を提供する機関が評価され、支援される時代へと完全に舵が切られます。
この大幅な予算増額は、国が認定制度を単なる規制ではなく、日本の日本語教育全体のブランド価値を高めるための重要な投資と捉えている証左です。
日本語学校が今すぐ押さえるべき3つの重要ポイント
ご存知の通り、認定制度では、審査ではこれまで以上に学校の実態が細かく見られています。
だからこそ、「何をどう準備すれば合格できるのか」を意識した取り組みが経営課題になります。
認定申請を「質保証戦略」への転換点と捉える
認定制度が始まったことで、審査では教育課程、教員組織、施設設備といった学校の実態がこれまで以上に細かく見られるようになりました。
だからこそ、「何をどう準備すれば認定基準をクリアできるのか」という視点は、重要な経営課題となります。
この認定申請を、単なる手続きと捉えるのではなく、自校の教育の質を抜本的に見直す絶好の機会と位置づけるべきです。
令和8年度概算要求に「カリキュラム編成・質向上支援事業」が新規で盛り込まれていることからも明らかなように、国の視線は日本語教育機関の「場所の数」から「教育の質」へと完全に移っています。この流れに乗り、申請をきっかけとして、自校のカリキュラムの整合性、教材の適切性、評価方法の妥当性を戦略的に再整備することが、これからの学校運営の土台を強固にします。
猶予期間を活かす「登録日本語教員」への計画的対応
認定制度の核となるのが、国家資格である「登録日本語教員」です。認定日本語教育機関では、一定の経過措置を経て、最終的にこの資格を持つ教員の配置が求められます。
現状、旧基準の要件を満たす教員も勤務できますが、それはあくまで数年間の「猶予」にすぎません。この猶予期間をどう活用するかが、将来の学校の安定運営を左右します。
「まだ時間がある」と考えるのではなく、今このうちから計画的に動くことが不可欠です。具体的には、現職教員がスムーズに資格を取得できるよう学校として全面的に支援する体制を整えつつ、今後の採用計画も「有資格者前提」で再設計することが急務です。
計画的な人材戦略こそが、将来の教員不足リスクを回避し、教育の質を維持・向上させる鍵となります
社会的価値を高める「地域との連携」の具体化
認定基準では、学習者に対する支援体制、特に生活オリエンテーションや相談体制の充実が評価項目として明記されています。その背景にあるのが、国の予算にも継続して計上されている「地域日本語教育の推進」という大きな方針です。
これからの日本語学校には、地域の自治体や企業と積極的に協力し、地域における多文化共生の拠点としての役割を果たすことが期待されています。
地域住民との交流イベントの開催や、地元企業への就職支援など、具体的な連携策を講じることは、単なる審査対策にとどまりません。それは、学校の社会的価値とブランドイメージを高め、地域社会に不可欠な存在として認知されるための、またとない機会となるのです。
概算要求から見える国の意図を経営に活かす
令和8年度概算要求は、日本語教育が「制度整備」から「質保証」へと進んでいく国の姿勢をはっきりと示しました。
この動きを理解することで、認定申請において何が問われるのか、日本語学校にどんな役割が期待されているのかがより明確になります。
認定申請は単なる手続きではなく、国の方向性を体現するプロセスです。
事前にこうした政策の流れを把握しておくことは、申請準備や学校運営をスムーズに進める上で大きな助けになります。
ぜひ文科省予算の動きを「自校の戦略を考えるヒント」として活用し、次の一歩に役立ててください。
次回申請に向けて、お悩みはありませんか?
- コースの組み立て方が分からない
- カリキュラムが基準を満たしているか不安
- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい
実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。