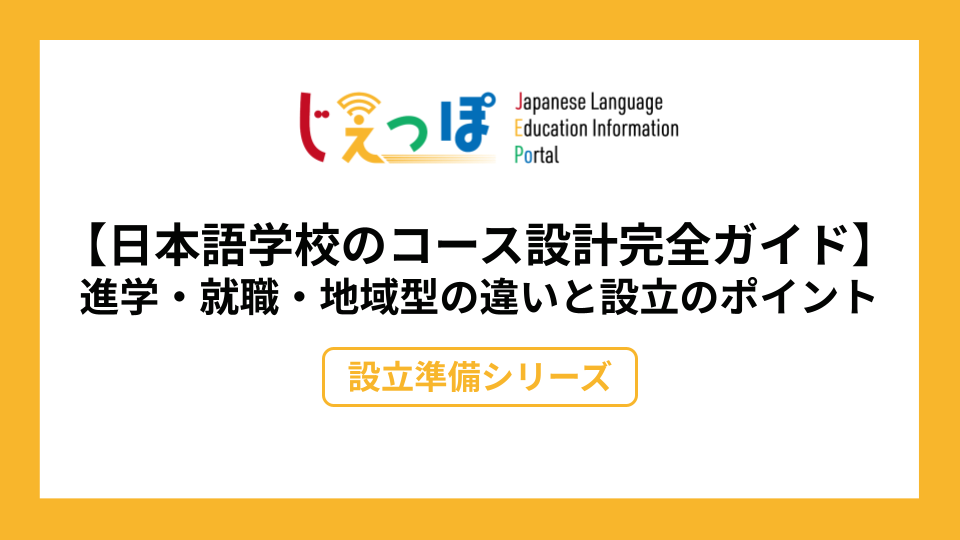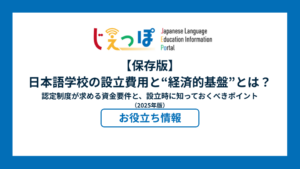日本語学校を新しくつくろうとするとき、最初に思い浮かぶのは「どんな校舎にするか」「教員をどう集めるか」といったことかもしれません。
もちろんそれらは大切ですが、実はそれだけでは十分ではありません。
2024年以降、留学生を受け入れるためには認定校であることが必須となり、認定校の審査では物件や教員配置と同じくらい、どんなコースを設計するか(教育課程の構成)が厳しく見られます。
コース設計が曖昧なまま準備を進めてしまうと、学則や申請書類の作成でやり直しが続き、思った以上に時間を取られることもあります。
だからこそ、学校づくりの出発点として 「どんな学生を育てたいのか」「そのためにどんなコースが必要か」 をしっかり考えることが大切です。
この記事では、日本語学校のコース設計を進めるうえで欠かせない視点を整理してご紹介します。
認定校の設立に関してもっと具体的な流れを知りたい方は、無料相談もご利用いただけます。
認定校として日本語学校を設立したい方へ
認定制度に基づいた正しいステップで準備を進めたい方のために、
無料で専門コンサルタントがご相談に対応します。
対象:設立検討中/制度に不安がある方
学校の設立目的を明確にする
日本語学校のコース設計を考えるうえで、最初に立ち返るべき問いは「この学校をなぜつくるのか?」という設立目的です。
目的が定まらないまま進めてしまうと、教育課程の設計や学生募集の方向性がぶれ、結果的に学則や申請書類の修正が何度も必要になってしまいます。
日本語学校の設立目的は、大きく次のように分けられます。
- 進学支援型:大学・大学院・専門学校への進学をゴールとする。到達目標はCEFR B2(JLPT N2相当)が一般的。
- 就職支援型:特定技能や一般就労を想定し、CEFR B1〜B2程度の日本語力と特定技能試験への対応を重視。
- 地域貢献・定着型:進学や就職を通じて、地方都市での就労や生活定着を目指す。日常会話力や地域理解を重視。
- 交流・教養型:日本語と日本文化を学ぶこと自体を目的とする。修了後に進学や就職をせず、一定期間の学習を終えたら帰国し、自国での日本文化理解や継続学習を支援する。
設立目的が定まると、自然と必要な到達レベル・授業時間数・学費水準・募集国といった具体的な設計要素が見えてきます。
学生に必要な日本語能力を設定する
コース設計の核心は「卒業時に学生をどのレベルまで到達させるか」です。これは単に教育目標を定めるだけでなく、在留資格・課程の認定要件に直結するため、慎重に設定する必要があります。
進学支援型の課程の場合
卒業後に大学や専門学校へ進学させる場合は、どんな学習期間であってもCEFR B2(JLPT N2相当)に到達させることが必須です。※よくある質問集Q2-7-46「大学や専門学校等、高等教育機関への進学を目標とする課程については、日本語能力の到達目標は B2 以上とすることが必要です。」
- 2年課程なら段階的にB2に到達させるカリキュラム
- 2年より短い期間での学習期間の場合は、入学時の日本語能力は高水準が求められる
つまり、課程の長さにかかわらず 「B2に到達させるための学習内容と到達目標」を明確に定義する必要があります。
就職支援型の課程の場合
就職を目的とする場合、一般的には CEFR B1〜B2程度 が目安です。
ただし重要なのは、留学のための課程の中には必ず「B2を目指すコース」を設けなければならない点です。
そのため就職志向のコースを設計する際には、就職先で求められる日本語力を明確にしたうえで、学習期間や入学時のレベルに応じて複数の到達目標を設定する のが現実的です。
交流・教養型の課程の場合
交流・教養型の課程は、日本語や日本文化を学ぶこと自体を目的とする学生を対象にしたものです。卒業後に進学や就職を前提としないケースが多く、1年以上の課程を設置する一方で、別枠で数週間〜数か月の短期プログラムをあわせて設けている学校も少なくありません。
このタイプの課程では、進学支援や就職支援のような到達レベルの明確な基準は設けられていません。そのため、どのような到達目標を設定するかによって学校の特色がそのまま反映されることになります。
ただし、在留資格「留学」に基づく課程として設置する以上、少なくとも一つはCEFR B2を目標とする課程を置くことが必須です。交流・教養型の課程を設計する場合も、この要件を踏まえて全体像を考える必要があります。
到達レベルをゴールに設定する
ゴールは、単にレベルや資格名を示すだけでなく、「何ができるようになるのか(Can-Do)」の形で具体的に示すことが重要です。
進学課程の例
- 「大学進学に必要なJLPT N2に合格できる」
- 「専門学校の講義を理解し、レポートや発表ができる」
就職課程の例
- 「特定技能試験に合格できる日本語力を身につける」
- 「職場で指示を理解し、同僚と協力して業務を遂行できる」
地域貢献・定着課程の例
- 「地域で就労できるレベルの会話力を持ち、生活に必要な情報を理解できる」
- 「地域イベントや交流活動に参加し、体験を日本語で共有できる」
交流・教養課程の例
- 「旅行や日常生活で必要なやり取りができる」
- 「自国の文化を日本語で紹介できる」
数値や資格とあわせて行動目標を提示することで、学則・募集要項・カリキュラムの一貫性を保つ基盤となります。
入学期をいつにするか
日本語学校のコース設計では、いつ学生を受け入れるか(入学期) も検討する必要があります。
入学期の設計は、学生募集のしやすさ・在校生のバランス・教員配置や時間割編成に直結します。
一般的な入学期のパターン
- 4月入学:日本の進学・就職の年度開始に合わせられるため、最も多くの学校が採用しています。2年間という最長の学習期間を設定できる点も大きなメリットです。
- 10月入学:4月に次いで需要が高い入学期です。進学型では1年6か月課程、就職型では1年や1年6か月課程などが一般的です。海外の卒業時期に合わせやすいため、留学生の募集がしやすい時期として人気があります。
- 7月・1月入学:4月・10月に加えて設ける学校もあります。特に設立から数年経ち、定員枠を拡大していきたい学校が追加で設定するケースが多いです。ただし1月入学は学習期間が短くなるため、入学希望者は比較的少ない傾向があります。
入学期を決めるときの検討ポイント
新規設立の学校や少人数規模の学校では、まず「4月+10月」の2期制に絞る方が運営しやすいといえます。
在留資格認定証明書(COE)の申請・交付手続きの体制が十分に整っていない段階で4期制を導入すると、事務局の業務が煩雑になりやすく、許可率の見通しも安定しにくくなります。その結果、予定以上に交付数が増えて対応が追いつかない、学生を受け入れられず説明対応が必要になる、といった想定外の事態を招くことがあります。
そのため、まずは需要が高い4月期と10月期から始め、体制や運営のノウハウが確立した段階で7月期や1月期の募集を検討するのが現実的です。
学生募集国を決める
日本語学校の多くは、まずは既存のエージェントや人脈がある国から学生を受け入れるケースが一般的です。
ただし、将来的に多角化や拡大を考えるなら、募集対象国をどう選ぶかは学校運営に直結する大事な判断になります。
ポイントとなるのは次のような点です。
学校の目的との適合性
進学志向の学生が多い国、就職志向が強い国など、それぞれ特徴があります。設立目的に合った国を選ぶことで在籍の安定や学習効果が高まりやすくなります。
書類の整備や申請のしやすさ
国によってCOE申請時に必要な書類の量や整合性に差があり、事務負担や許可率に影響します。
在籍時の安定性
学生の生活習慣や進路意識によって、退学率やトラブルの傾向は異なります。学校の規模やサポート体制に応じて無理のない範囲を選ぶことが大切です。
学校の特徴を考える
設立目的や育てたい学生像が定まると、そこから自然と「その学校ならではの特徴」が浮かび上がってきます。
この特徴を具体的に描いておくと、カリキュラムの設計やコース設定がスムーズになり、募集活動でも他校との差別化につながります。
学校の特徴となり得る要素
- 進学支援の手厚さ
例:進学希望の学生に対して、早い段階から個別面談や模擬面接を実施する。 - 就職支援の強化
例:特定技能試験対策、日本企業向けのビジネスマナー指導、企業説明会との連携。 - 学習環境の工夫
例:レベル別・少人数クラス編成。きめ細やかなレベルチェック。 - 課外活動や地域連携
例:地域住民との交流イベント、文化体験、ボランティア活動を豊富に設ける。 - 学習サポート体制
例:日本語学習の補習クラス、母語サポート、生活相談窓口の充実。
「どんな学生を育てたいか」を軸にして考えると、自然と特徴が形になっていきます。進学型なら「入試サポートに強い学校」、就職型なら「企業研修や職業体験に力を入れる学校」、地域貢献型なら「地域に根ざした課外活動が豊富な学校」といったように、目的と特徴が一貫する設計が理想です。
まとめ
日本語学校のコース設計は「制度要件を満たす」だけでは不十分です。
設立目的・教育目標・学生募集・学校の特徴をすべて踏まえて設計することが、安定した学校経営の第一歩となります。
新規校にとっては「最初の一手」、既存校にとっては「再成長のきっかけ」として、コース設計を戦略的に考えていきましょう。
日本語学校の設立を本格的に検討されている方へ
認定制度に即した設立準備や申請の流れについて、
専門コンサルタントが無料でアドバイスいたします。