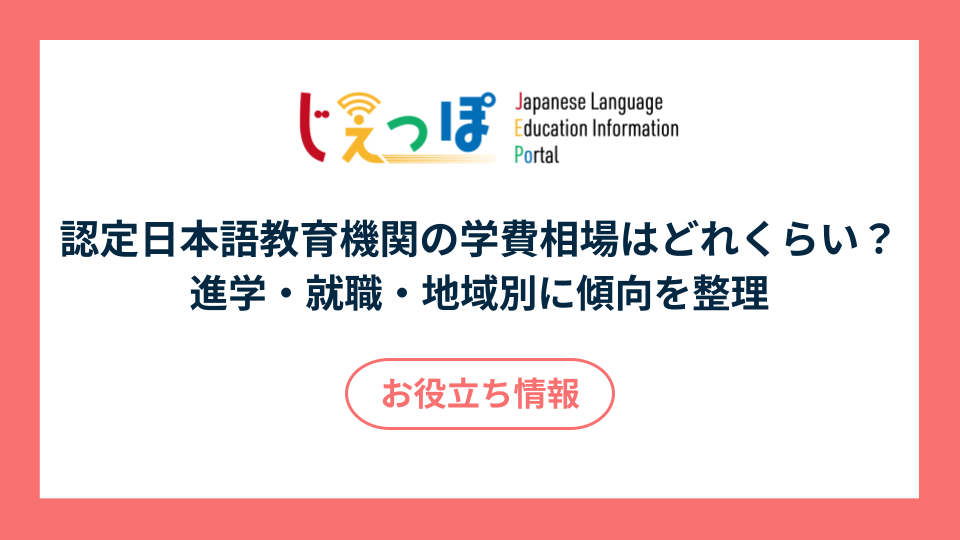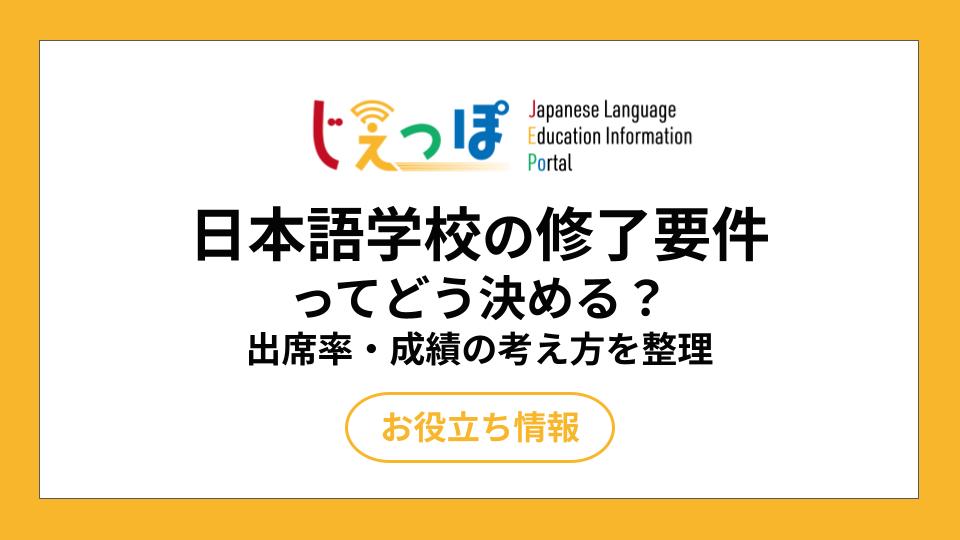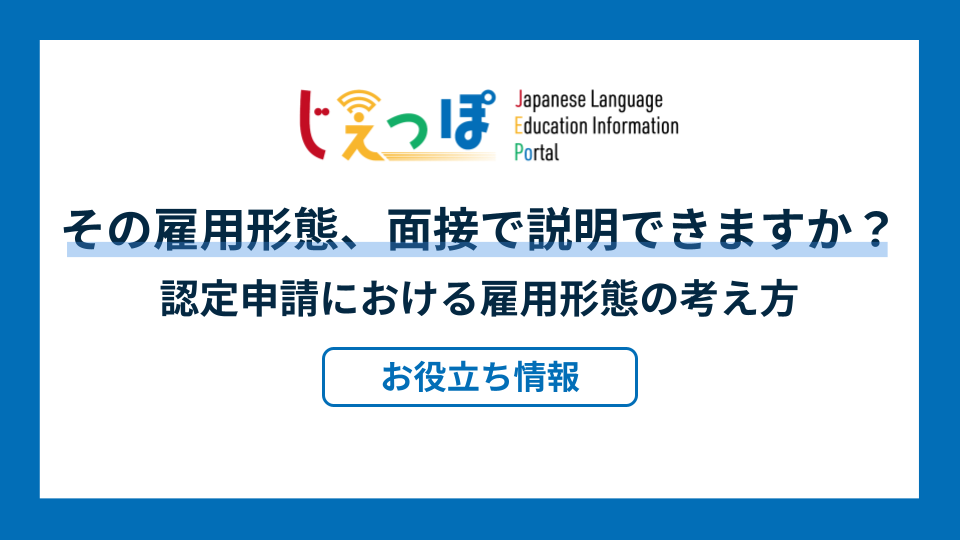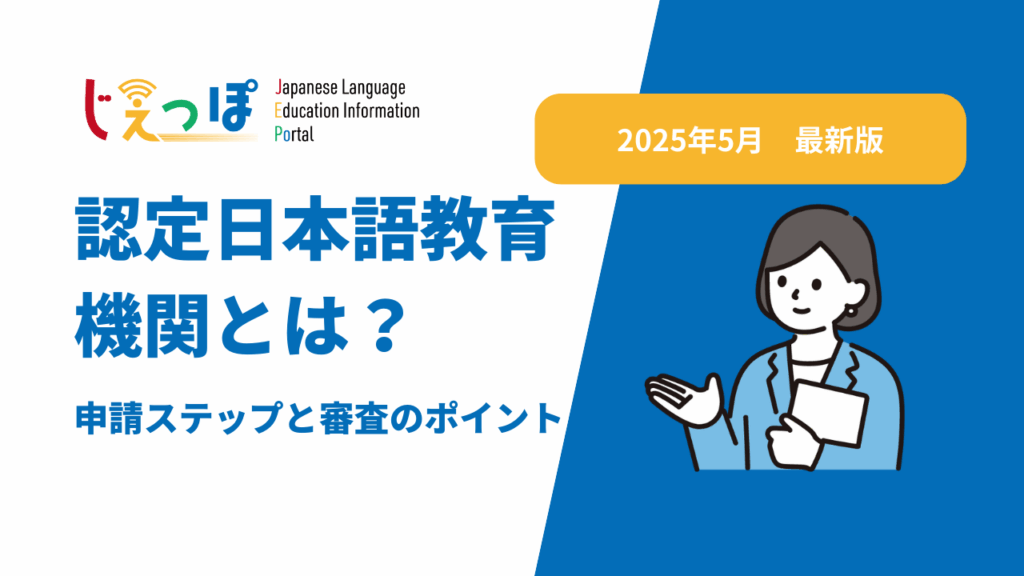
「認定校ってなに? 申請はいつ、なにをすればいいの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、本記事では2024年度に新たに施行された「認定日本語教育機関制度」の概要、申請の具体的なスケジュール、審査のポイントについてわかりやすく解説します。これから認定取得を目指す学校の皆様にとって、準備の道標となる内容を網羅しています。
認定日本語教育機関とは
認定日本語教育機関とは、文部科学省が実施する認定制度において「日本語教育の適正かつ確実な実施が可能」と認められた教育機関のことです。
これは、従来の法務省告示校制度に代わって2024年から本格的に導入された制度であり、出入国在留管理庁との連携のもとで、日本語教育の質を担保し、留学生の受け入れ体制を一層整備することを目的としています。
認定を受けるためには、教育課程、教職員体制、施設基準、学生支援体制などについて厳格な審査を受ける必要があります。
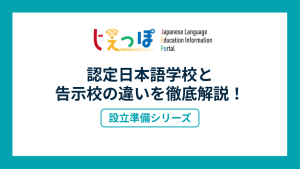
認定取得はなぜ必要なのか?
認定校としての認可は必須ではありません。ただし、下記の場合は認定を取得する必要があります。
留学生を受入れる場合は必ず認定校に
認定校であることにより、在留資格「留学」で滞在する外国人の受入れが可能になります。逆に言うと、外国人留学生を受け入れる日本語学校は必ず認定校でなければなりません。
認定申請の流れ
認定申請は、年に2回(4月申請と10月申請)に限って受け付けられます。申請には数か月にわたる準備が必要となるため、早めの計画が重要です。
ステップ1:認定申請書類の準備(目安:3か月前〜)
3カ月前から、下記の内容を含む申請書類を準備していきます。量が多いため準備期間を適切に確保しましょう。
- 学校理念・学生の進路イメージの確定、事業計画書の作成
- 必要人数の教職員の採用、履歴・資格証明の取得
- 教育課程(カリキュラム)の設計、作成
- 施設・設備・管理体制の構築
- 支援体制・出席管理・帳簿様式などの整備
ステップ2:申請提出(4~5月ごろ or 9~10月ごろ)
書類提出は、事前相談日(学校ごとに申し込む文科省との面談日)より前にすべて揃えて提出します。あらかじめスケジュールを確認しておきましょう。
- 申請等に必要な書類を全て揃え、事前相談日の14日(2週間)前までに電子システムを通じて日本語教育課へ提出
- 文部科学省が指定するフォーマット(申請書様式)で提出
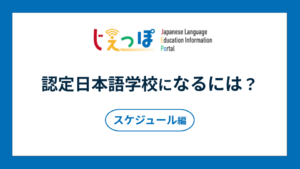
ステップ3:審査(書類審査/面接審査/実地審査)
申請後、一次審査、二次審査が行われます。審査には、書類審査、面接審査、実地審査が含まれます。
- 認定基準への適合性、書類の整合性を確認する書類審査
- 設置者・校長・主任教員への面接審査
- 学校施設の実地審査
ステップ4:結果通知(提出から約6か月後)
4月の申請時期の場合は10月ごろ、10月の申請時期の場合は翌年4月ごろに認定結果が公表されます。
- 合否通知とともに、必要に応じて「留意事項」が通知されます
- 不可の場合も申請機関名等が公表されます
- ただし、審査の過程で不可になる可能性が高い場合は、その旨が通知され、取り下げを行うことができます
審査で見られるポイント
認定審査では、以下のような観点が確認され、それぞれの整合性や、運営上の懸念も考慮された上で総合的に評価されます。
設置者の適格性
- 設置者の法的・組織的安定性
- 財務的健全性(債務超過でないかなど)
- 運営能力(日本語教育機関の運営に必要な知識・経験)
- 社会的信頼性及び法令順守状況
教職員の配置・資格・体制
- 校長(・副校長)の適格性と配置
- 主任教員の適格性と配置
- 教員及び本務等教員の配置
- 教員の資格及び担当授業時数の適切性
- 事務体制及び研修体制の整備状況
施設及び設備
- 校地・校舎の位置及び環境
- 校地・校舎の保有形態及び面積
- 校舎内の施設(教室・教員室・事務室・図書室・保健室等)の整備状況
- 教室の環境及び設備
教育課程の編成及び実施方法
- 教育課程の目的・目標設定の適切性
- 教育課程の体系性・内容の適切性
- 授業時間数・期間等の適切性
- 授業実施方法・学習評価の適切性
- 入学者の募集・選考の適切性
学習上及び生活上の支援体制
- 学習上の困難を抱える生徒への支援体制
- 出席管理及び指導体制
- 災害時等の学習継続支援体制
- 生活指導・進路指導体制
- 健康管理支援体制
- 在留継続支援体制
- 関係機関との連携体制
情報公開、自己点検・評価、帳簿管理等の運営体制
- 情報公開の適切性
- 自己点検・評価の実施体制と内容の適切性
- 帳簿の備付け・管理・保存の適切性
- 定期報告及び変更届出の体制
不認定になるケースとその対策
認定申請は、これまで2回の結果が公表されています。認定になった学校は第1回が30.6%、第2回が39.6%と不認定見込みのため取り下げた学校も少なくありません。以下のようなケースには特に注意が必要です。
❌ 書類の不備や整合性の欠如
- 提出書類に矛盾がある
- 必要書類が漏れている
- 認定基準に不適合の項目がある
- 学校理念を実現するカリキュラム・目標設定になっていない
- カリキュラムや要員配置に不整合がある など
❌ 担当者の制度・書類内容理解不足
- 認定制度の趣旨を把握していない
- 手引きや基準に沿った書類作成ができていない
- 面接審査でカリキュラムの内容に基づいた回答ができない
- 面接審査で出席者(設置者・校長・主任教員)間で回答に齟齬がある
- 面接審査当日に体制を考える など
❌ 運営体制の構築が不十分・準備不足
- 書類で示された出席管理や研修の体制が実際の運営とかけ離れている
- 支援体制の説明に裏付けがない
- 学生募集・生活指導・進路指導の担当者と担当業務が具体的に分担できていない など
対策のポイント
内部研修の実施:関係者に制度趣旨を共有
認定申請を成功させるには、関係者が適切に制度理解を深めることが重要です。
第三者レビューの活用:専門家に事前確認を依頼
不安な場合は、認定申請に精通した専門家のサポートを活用することも一つの手です。事前に確認すべきポイントの確認や対策を行ってから申請に臨むことができます。
おわりに
認定日本語教育機関の制度は、単なる「申請書類の提出」ではなく、学校としての教育の質や運営体制が問われる仕組みです。申請にあたっては、制度の趣旨を正しく理解し、内部体制の整備と十分な準備が不可欠です。
初めて申請を検討される方にとっては、不安や疑問も多いかと思いますが、適切な情報と支援を得ることで、着実に準備を進めることができます。制度への対応を「負担」と捉えるのではなく、学校の質を高める機会として前向きに取り組むことが、認定取得への近道となるでしょう。
認定申請に関して「何から手をつければいいかわからない」「自校の準備状況を確認したい」とお考えの方は、ぜひチェックリストの活用や無料相談をご検討ください。皆様の認定取得に向けた取り組みを、私たちも全力でサポートいたします。
※本記事は2025年5月時点の法令・制度をもとに作成されています。
【おすすめ記事リンク】
次回申請に向けて、お悩みはありませんか?
- コースの組み立て方が分からない
- カリキュラムが基準を満たしているか不安
- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい
実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。