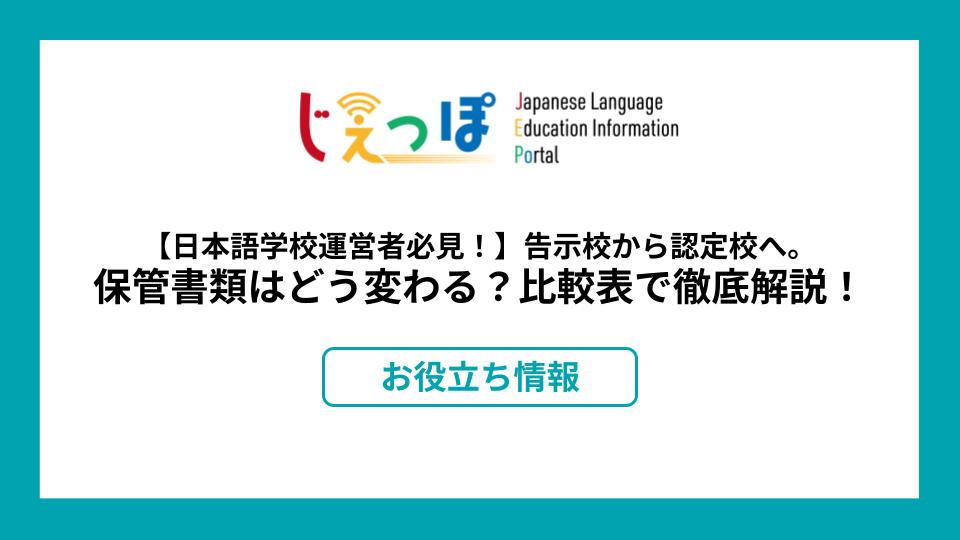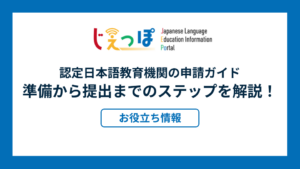日本語学校の運営者の皆さん、こんにちは!
2024年4月に認定法が施行され、日本語学校の運営は大きな転換期を迎えていますね。
これまでの法務省管轄の「告示校」から、文部科学省が認定する「認定校」への移行。
「具体的に何が変わるの?」「特にバックオフィスの書類管理はどうしたら…?」と、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、告示校が守るべき「告示基準」と、これから認定校が従う「認定法」及び「施行規則」を徹底比較!
皆さんが一番知りたい【保管すべき書類】に焦点を当て、分かりやすい比較対照表を使いながら、変更点と対応のポイントをズバリ解説します!
この記事を読めば、
- 告示校と認定校で、保管書類がどう違うのかが分かる!
- 新しく保管が必要になる書類と、その期間が分かる!
- 2029年までの移行期間に、今から何をすべきかが分かる!
認定校へのスムーズな移行に向けて、一緒に準備を始めましょう!
認定申請、気になっていませんか?
「うちも申請すべきなのかな…」
「どのコースで申請すればいいか分からない」
そんなお悩みは、制度と実務に詳しいスタッフが無料でご相談を承ります。
(初回ご相談無料・Zoom対応OK)
なぜ今、書類管理の見直しが必要なの?「告示校」と「認定校」のおさらい
まずは基本の確認から!「告示校」と「認定校」は、管轄省庁と準拠するルールが異なります。
- 告示校(これまで)
- 管轄: 法務省(出入国在留管理庁)
- ルール: 日本語教育機関の告示基準
- 目的: 「留学」の在留資格を付与するための基準を満たしているか。
- 認定校(これから)
- 管轄: 文部科学省
- ルール: 日本語教育機関認定法、同施行規則など
- 目的: 日本語教育の質を保証し、適正かつ確実に実施できる機関であるか。
2029年4月以降も「留学」の在留資格を持つ学生を受け入れるには、文科省の「認定校」になる必要があります。
そして、この認定を受けるための審査や、認定後の監査では、法令に則った適切な書類管理ができているかが厳しくチェックされます。
つまり、書類管理は単なる事務作業ではなく、学校の信頼性そのものを示す重要な指標になるのです。
【比較対照表】告示校 vs 認定校 保管すべき書類一覧
それでは、本題の比較対照表を見ていきましょう!
特に大きく変わる点や、新たに追加された項目に注目してください。
| 書類の種類 | 【告示校】保管内容・期限・根拠 | 【認定校】保管内容・期限・根拠 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1. 入学希望者への情報提供記録 | 募集に係る修業期間の始期から3年 (告示基準 第1条31号) | 【帳簿に包含】 学則や募集要項の公開義務があり、関連書類は帳簿の一部として保管。 (法 第3条、施行規則 第4条、第10条) | 認定校では「帳簿」として一元管理する意識が重要。情報公開の透明性がより求められます。 |
| 2. 入学者選考に関する記録 | 申請に係る修業期間の始期から3年 (告示基準 第1条35号) | 【帳簿】記載の日から5年 (法 第10条、施行規則 第10条1項四号, 2項) | 保管期間が延長! 選考プロセスの透明性を証明する重要書類です。 |
| 3. 生徒の出席記録 | 在籍しなくなってから1年 (告示基準 第1条36号) | 【帳簿】記載の日から5年 (法 第10条、施行規則 第10条1項三号, 2項) | 保管期間が大幅に延長! 従来の管理方法では対応できない可能性も。デジタル化の検討を。 |
| 4. 生徒の学習・学籍記録 | (明確な規定なし) | 【帳簿】 ●学習状況の記録:記載の日から5年 ●入学・卒業等の学籍記録:記載の日から20年 (法 第10条、施行規則 第10条1項三号, 2項) | 超重要変更点! 特に学籍に関する記録は20年という長期保管義務が課されます。 |
| 5. 生徒への指導記録 | 出席率低下者への指導記録:在籍しなくなってから1年 (告示基準 第1条37号) | 【帳簿】学習上・生活上の支援の実施状況として記載の日から5年 (法 第10条、施行規則 第10条1項五号, 2項) | 指導内容が「生徒支援」として包括的に管理されます。生活指導や進路指導の記録も含まれます。 |
| 6. 資格外活動許可に関する記録 | 許可の有無・内容の把握、アルバイト先の届出内容を、在籍しなくなってから1年保存 (告示基準 第1条40号) | 【帳簿に包含】 直接の規定はないが、「生活上の支援の実施状況」の一部として、関連する指導記録や届出内容を5年間保存すべき。 (施行規則 第10条1項五号, 2項) | 認定校になっても入管法上の在籍管理責任は継続します。法務省への報告義務との関連で、保管は必須と考えましょう。生活指導の一環として記録する意識が重要です。 |
| 7. 教職員に関する記録 | (明確な規定なし) | 【帳簿】氏名、履歴、出勤状況、担当授業などを記載し、5年保存 (法 第10条、施行規則 第10条1項二号, 2項) | 新規義務! 教員の資格(登録日本語教員)や配置、勤務実態を証明するために不可欠な記録です。 |
| 8. 財務・経理に関する記録 | (明確な規定なし) | 【帳簿】資産、出納、経費の予算決算、備品目録などを記載し、5年保存 (法 第10条、施行規則 第10条1項六号, 2項) | 新規義務! 学校運営の健全性を示すための重要項目。会計の透明化が求められます。 |
| 9. 健康診断に関する記録 | (明確な規定なし) | 【帳簿】生徒の健康状況、健康診断の実施状況を記載し、5年保存 (法 第10条、施行規則 第10条1項七号, 2項) | 新規義務! 生徒の健康管理も学校の責務として明確に記録・保管する必要があります。 |
| 10. 定期点検・報告の根拠資料 | 基準適合性点検の確認資料:報告から3年 (告示基準 第1条45号) | 【帳簿が根拠資料に】 自己点検(法8条)や定期報告(法9条)の根拠となるため、帳簿類は5年以上の保管が必須。 (法 第8条, 9条, 10条) | 点検や報告の際に「あの書類はどこ?」とならないよう、日々の帳簿記録が全ての基礎になります。 |
主要な保管書類の変更点と注意点を深掘り解説!
比較表を見て、「うわ、大変そう…」と感じたかもしれませんね。大丈夫です!特に重要なポイントを3つに絞って、分かりやすく解説します!
① 保管義務の根幹となる「帳簿」が新設された!
ここが一番の変更点!
認定法第10条では、新たに「帳簿」の備付けと保存が義務化されました。これまで告示基準で個別に定められていた記録義務が、学校運営のほぼ全てを網羅する「帳簿」という形で一元化・強化されたイメージです。
この「帳簿」に記載すべき内容は、施行規則第10条で細かく定められています。
- 教育活動: 日課、教材、日ごとの活動状況
- 教職員: 履歴、出勤状況、担当授業
- 生徒: 学習・出席状況、募集・選考、成績
- 支援: 学習上・生活上の支援状況
- 財務: 資産、出納、予算決算、備品
- 健康: 健康状況、健康診断の実施状況
これらをきちんと記録することが、認定校の運営の土台となります。
② 保管期間が「5年」、学籍関連は「20年」に!
これが実務上、最もインパクトの大きい変更点です!
これまで「1年」や「3年」だった保管期間が、原則「5年」に延長されます。
そして、特に注意が必要なのが、生徒の入学・卒業といった「学籍に関する記録」です。
紙媒体での保管だけでは、場所の確保も劣化対策も非常に困難です。今のうちからデータでの管理・保存体制(デジタル化)を本格的に検討し、準備を進めることを強くお勧めします。
③ 教職員・財務・健康に関する記録が明確に義務化された!
告示基準では、生徒の在籍管理に関する記録が中心でしたが、認定法では学校運営そのものの透明性が問われます。
- 教職員の記録: 「登録日本語教員」が適切に配置され、稼働しているかを証明するために必須です。
- 財務の記録: 健全な学校経営が行われているかを示す根拠となります。
- 健康診断の記録: 生徒の心身の健康を守るという、教育機関としての責務を果たすための記録です。
これらの記録は、監査時だけでなく、学校のガバナンスを強化し、保護者や入学希望者からの信頼を得るためにも非常に重要になります。
まとめ:変化をチャンスに!質の高い学校運営を目指して
今回は、告示校から認定校への移行に伴う「保管書類」の変更点について解説しました。
- 認定法では運営全般を網羅する「帳簿」の作成・保管が義務化!
- 保管期間は原則5年、学籍に関する記録は20年へと大幅に延長!
- 教職員、財務、健康など、学校運営の透明性を示す記録が求められる!
確かに、やるべきことは増え、事務的な負担は大きくなるかもしれません。
しかし、この法改正は、日本の日本語教育全体の質を高め、留学生が安心して学べる環境を整備するための重要な一歩です。
適切な書類管理は、コンプライアンスを守るだけでなく、学校運営の質そのものを高め、内外からの信頼を勝ち取るための強力な武器となります。
移行期間はまだ残されています。ぜひこの記事を参考に、早め早めの準備を進め、来るべき認定審査に万全の体制で臨んでください。
この変化をチャンスと捉え、より質の高い日本語学校を目指していきましょう!
もちろん、具体的な帳簿の作り方やデジタル化の進め方など、お困りのことがあれば、いつでも私たち専門家にご相談くださいね。
次回申請に向けて、お悩みはありませんか?
- コースの組み立て方が分からない
- カリキュラムが基準を満たしているか不安
- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい
実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。