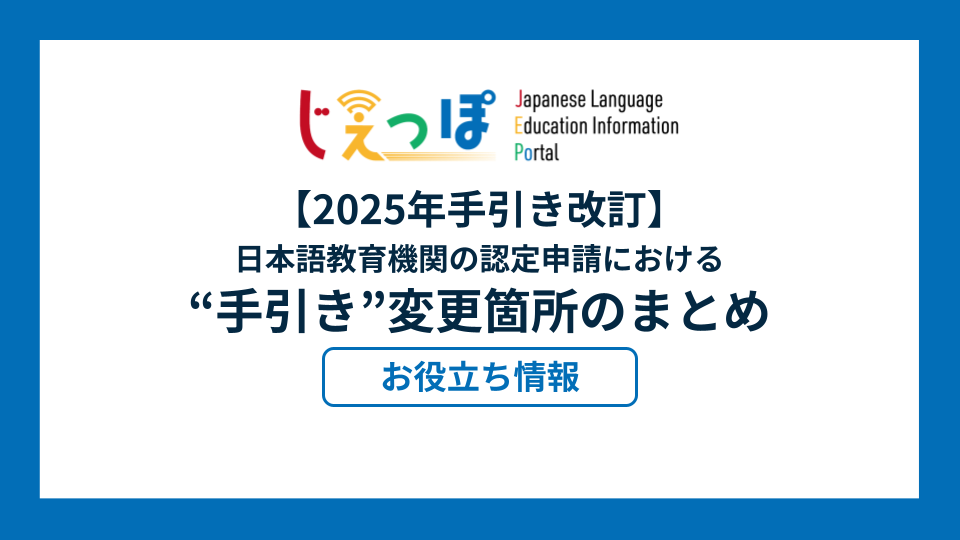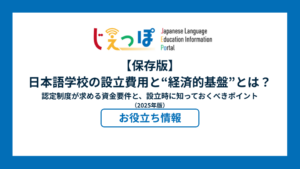2025年5月、認定申請を考えている日本語学校にとって見逃せない「手引き」の改訂が発表されました。この記事では、告示校の関係者や新しく日本語学校をつくろうとしている方に向けて、今回の変更ポイントをわかりやすく整理してご紹介します。
認定申請、気になっていませんか?
「うちも申請すべきなのかな…」
「どのコースで申請すればいいか分からない」
そんなお悩みは、制度と実務に詳しいスタッフが無料でご相談を承ります。
(初回ご相談無料・Zoom対応OK)
認定申請の“締切”が明確に:2028年春申請がラストチャンス
これまで、既存の法務省告示機関は「令和11年3月31日までに認定を受けなければ、留学生の受け入れができなくなる」とされていましたが、今回の改訂ではこの条件を満たすために必要なスケジュールが具体的に示されました。
結論から言えば、2028年春(令和10年度)申請が実質的に最後のチャンスになります。この申請に間に合って認定を受けなければ、それ以降は留学生の受け入れができなくなります。今から逆算して、しっかり準備を進めましょう。
2028年の春申請の認定で「不可」となってしまうと、留学生の受け入れが止まってしまうので注意が必要です!
何が審査されるの?そのチェックリストが公開!
今回の改訂では、審査で見られるポイントと、それに対応する書類や根拠文書が整理されて一覧で公開されました。これにより、「どの資料をどう準備すればいいか?」がわかりやすくなり、準備の漏れやミスを防げるようになりました。
こちらのリンクのページから、項目の一覧がダウンロードできます。
申請件数の制限がなくなった!
これまで、「1回の申請で受け付けられる件数(申請機関数)には上限があるかも」という不安がありましたが、今回の手引きからはその記載(下記参照)が削除されました。つまり、申請件数の上限が撤廃された可能性が高いと考えられます。
移行措置期間中においては、申請時に法務省告示機関である日本語教育機関については、事前相談を受けた場合でも、申請希望件数が多数に上り、審査可能な件数を大幅に上回る等やむを得ない事情がある場合には、次回以降の申請の受付期間において申請をしていただくこととなる場合があるため、あらかじめご承知いただきたい。
ファイル名にもルールが!提出時は要注意
提出書類のファイル名のつけ方についても、より細かく指定されるようになりました。ちょっとしたことですが、形式のミスで受理されない……なんてことのないように、手引きに記載されたルールに沿ってファイル名を整えてくださいね。
各様式の注意点がより実務的に
それぞれの提出資料について、注意しておきたいポイントが追加されました。一部を抜粋してご紹介します:
- 添付(7):教育以外の事業がある場合、その事業の内容や概要も書きましょう。
- 様式2:午前・午後コースで授業時間帯だけが違う場合は、1つの課程としてまとめてOK。
- 様式4-2:右上の年月日は「就任承諾日」か「宣誓日」を書くように。
- 添付(4):決算日と学校開設予定が離れている場合、追加資料を求められることがあります。
- 様式6-3:告示校・認定校以外でも、日本語教育の経験があれば記載してOK。
- 様式6-4、6-6:記入の参考になる記載例が新しく追加されました。
- 様式7:年間指導時間の根拠は、かっこ書きで丁寧に記載(例:〇時間×〇回×〇人)。
- 様式10-1:「学生が学習を自分で管理できるようになるか?」についても記載が必要です。
- 様式10-1~10-5:課程外の授業をカウントする場合は、その旨を明記。
- 添付書類11~14:資料は番号順ではなく、教員ごとにまとめる方式です。
認定後の対応にも新ルール
認定を取得したあとに「課程を増やしたい」「定員を変更したい」となった場合の書類の作り方や手続き方法についても、今回の手引きに新たな記載が追加されました。
さらに、定員を増やす際の注意点として、「事前相談のとき」ではなく、「届出時点で現定員の8割を超えていること」が条件になるという点も加わっています。
変更届の「30日前ルール」がなくなった!?
以前は「変更の30日前までに届け出が必要」とされていた変更届の期限が、今回の改訂で明記されなくなりました。場合により30日前までに届け出ができない場合について考慮された可能性があります。
おわりに|今こそ、準備をスタートするタイミング!
今回の改訂は、制度の考え方や実務の細かい部分まで大きく見直された内容となっています。特に、2028年春が認定申請の最後のチャンスになることが明記された今、タイムリミットを意識した動きが求められます。
これから申請を目指す方も、すでに準備を始めている方も、手引きの最新版をしっかり読み込み、ひとつずつ確実に進めていきましょう!
次回申請に向けて、お悩みはありませんか?
- コースの組み立て方が分からない
- カリキュラムが基準を満たしているか不安
- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい
実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。