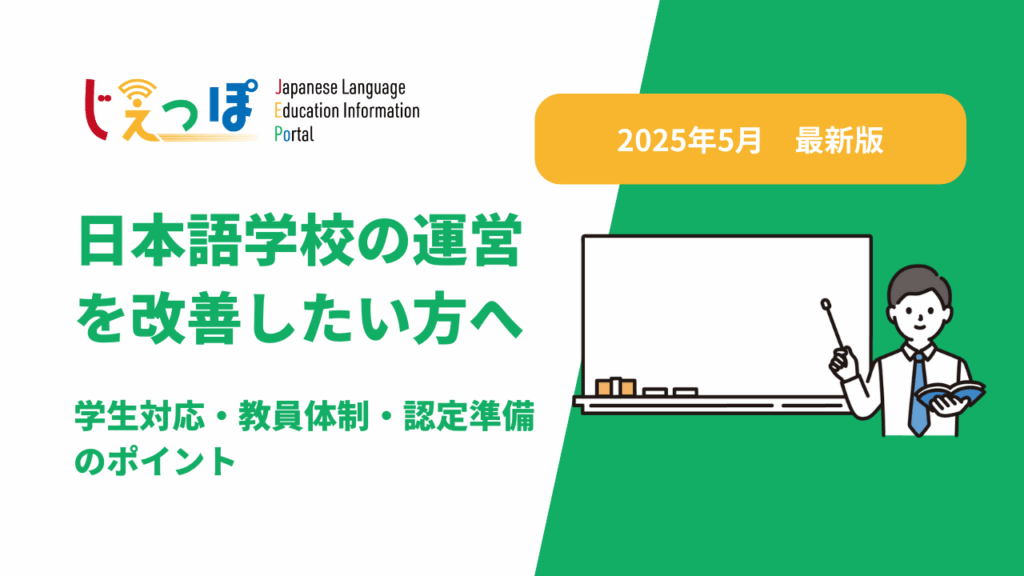
日本語学校の運営において、「学生管理が不安定」「教員が確保できない」「認定制度への対応が負担」という声が多く聞かれるようになってきました。
特に2024年にスタートした「認定日本語教育機関制度」は、制度対応にとどまらず、学校全体の体制を見直すチャンスでもあります。
本記事では、現場で実際に起きている課題をもとに、以下の3つの観点から運営改善のヒントをお届けします:
- 学生対応(生活指導・進路支援など)
- 教員体制・労務の整備
- 認定制度を活かした体制づくり
「制度対応に追われる」のではなく、「制度を活かして学校を強くする」視点で、ぜひ今一度、運営を見直してみてください。
認定申請、気になっていませんか?
「うちも申請すべきなのかな…」
「どのコースで申請すればいいか分からない」
そんなお悩みは、制度と実務に詳しいスタッフが無料でご相談を承ります。
(初回ご相談無料・Zoom対応OK)
学生対応・生活・進路支援
外国人増加による日本語学校の運営リスク
外国人留学生の数は年々回復・増加傾向にあり、日本語学校への期待も再び高まっています。特に東南アジア・南アジア諸国からの留学生が増えており、コロナによって定員数を減らした学校でも、活況を受けてコロナ前の水準へ戻す動きが見られます。
しかしその一方で、受け入れる側の日本語学校にとっては、学生対応の負荷が急増しているのも事実です。特に以下のようなリスクが顕在化しています:
- 出席不良・失踪などによる在留資格上の問題(日本語学校へのカウント)
- 日本での生活支援が不十分なことによる近隣の住民や施設等とのトラブル
- 学生ニーズの多様化による学生の不安・不満の蓄積
こうした背景から、今求められているのは、単なる「学生数の確保」ではなく、一人ひとりの学生に対するきめ細かな管理と支援体制の構築です。
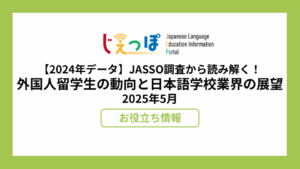
適正校Ⅰを目指す/維持することで得られるメリット
外国人留学生の増加に伴い、今後は在留資格認定証明書(COE)の審査が全国的に厳格化される可能性があります。これにより、学生管理や生活指導体制に関する疑義がある学校では、交付率の低下や審査遅延といったリスクが生じることが予想されます。
こうした中で、「適正校Ⅰ」に分類されている学校には以下のような明確なメリットがあります:
- COE申請時の提出書類が少なくなる(日本語能力を示す資料や経費支弁書等を省略可)
- 審査時に確認される書類が少ないため、結果として交付率の低下リスクが抑えられる
- 国や地域に関係なく提出書類が簡素化されるため、学校側の事務負担も少なくなる
つまり、「適正校Ⅰ」であり続けることが、将来的な制度変更や審査厳格化にも強い運営体制を確保する鍵となります。
適正校の維持には、出席管理・生活指導体制の安定・丁寧な学生支援の実施といった日常の運営が問われるため、今のうちから体制整備に取り組んでおくことが重要です。
教員体制・労務関係
教員不足の深刻化と構造的な課題
日本語教育業界では、教員不足が恒常的な課題となっています。とくに専任教員の確保や若手人材の定着が難しく、全国の多くの学校で同じような悩みが共有されています。
背景には、以下のような構造的な問題が存在します:
- どの学校も似たような働き方・給与水準・授業内容であるため、教員が短期間で他校へ流れやすく、平均在籍期間が短くなりがち
- 主任教員以外の役職やキャリアパスがない学校が多く、長期的にスキルアップ・昇進しにくい
- 慢性的な低賃金により、若い世代や未経験から参入した教員が生活を維持しづらく、結果的に別業種に流れてしまう
また、教える内容や教材が固定化されやすく、現場に創意工夫の余地が少ない環境も、教員のやりがいを失わせる一因です。
そのため、「数が足りない」という課題だけでなく、「教員が育たない・定着しない・モチベーションを維持できない」という根本的な構造の見直しが求められています。
認定制度に向けた教員の獲得競争へ
2024年に施行された日本語教育機関の認定制度では、新たに国家資格である「登録日本語教員」であることが求められます(※一定の経過措置あり)。
しかし、現場の声としては「すでに高齢の教員など、途中で諦めてしまう人も多い」といった懸念が上がっています。
こうした背景から、学校側がどのように教員の資格取得を支援できるかが、今後の教員採用・定着の分岐点になります。多くの学校では、受験費用の補助や、校内勉強会の開催等を導入し始めています。
加えて、認定制度では、学生40人に専任教員1人という配置基準であるため、現在告示校に適用されている「50人に1人」から引き下がることとなります。これにより、全国的に教員の「奪い合い」がより一層激しくなると予測されます。
だからこそ今後は、
- 「この学校でならスキルが身につく」
- 「役職や評価の仕組みがあり、成長の道が見える」
- 「資格取得後も活躍できるフィールドがある」
といった魅力を打ち出せる学校が、教員から選ばれる時代になります。
なお、認定申請時には「教職員の研修計画」の提出が求められています。認定申請の準備の面からも、校内でのキャリアアップの仕組み作りや成長支援体制の整備が必要不可欠となります。
差別化と実質的なキャリア形成の支援こそが、これからの教員確保戦略の要といえるでしょう。
認定制度を“体制改善”のきっかけにする
認定制度に対応するというと、「複雑な書類をそろえる作業」「基準を満たすための負担」といったネガティブな印象を持たれがちです。
しかし、認定申請は単なる事務作業ではなく、学校全体の運営を見直す絶好の機会でもあります。
認定制度は、制度の根幹として「学生にとってわかりやすく、質の高い日本語教育を提供すること」を目的としています。そのため、審査では以下のような点が重視されます:
- 学校案内・募集要項・オリエンテーション資料が学生にとって分かりやすいものになっているか
- 学生生活を支える仕組み(生活相談・出席管理・進路指導)が実際に機能しているか
- 教務・事務・支援が一体となった体制が構築されているか
つまり、認定申請に必要な書類を準備する過程自体が、学校運営を可視化し、課題を洗い出し、改善するためのフレームワークになっているのです。
たとえば:
- 「募集要項が日本語中上級レベルの学生にとってわかりにくい」
- 「オリエンテーション内容が毎年変わり、記録や改善が残っていない」
- 「進路指導が一部教職員に依存していて、仕組み化されていない」
こうした点に気づくことこそが、認定申請の価値ともいえます。
結果として、認定校としての信頼性が高まるだけでなく、学生満足度や定着率、職員間の連携といった日常運営にも好影響をもたらします。
「認定を取るため」ではなく、「いい学校をつくるために認定制度を活用する」という視点が、今こそ求められています。
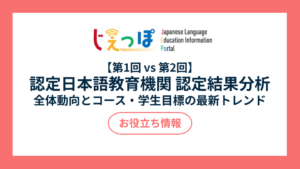
おわりに
日本語学校の運営は、学生対応、教職員の体制整備、そして制度対応と、年々複雑化しています。
特に認定制度の導入により、これまでの「とりあえず回す運営」から、質の高い教育と管理体制を備えた“選ばれる学校”へと転換することが求められる時代になりました。
とはいえ、すべてを一度に見直すのは現実的ではありません。だからこそ、まずは自校の現状を整理し、できるところから改善を始めることが大切です。
- 学生への説明資料、ちゃんと「伝わる日本語」になっているか?
- 教員がやりがいを感じて働ける環境はあるか?
- 認定申請の準備を、体制強化のチャンスとして活かせているか?
こうした問いに向き合うことが、結果的に学生にも、職員にも、地域にも信頼される学校づくりにつながります。
「認定取得を目指す」だけでなく、「よりよい学校運営をつくるために制度を活かす」視点で、ぜひ今こそ運営の見直しに取り組んでみてください。
次回申請に向けて、お悩みはありませんか?
- コースの組み立て方が分からない
- カリキュラムが基準を満たしているか不安
- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい
実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。
