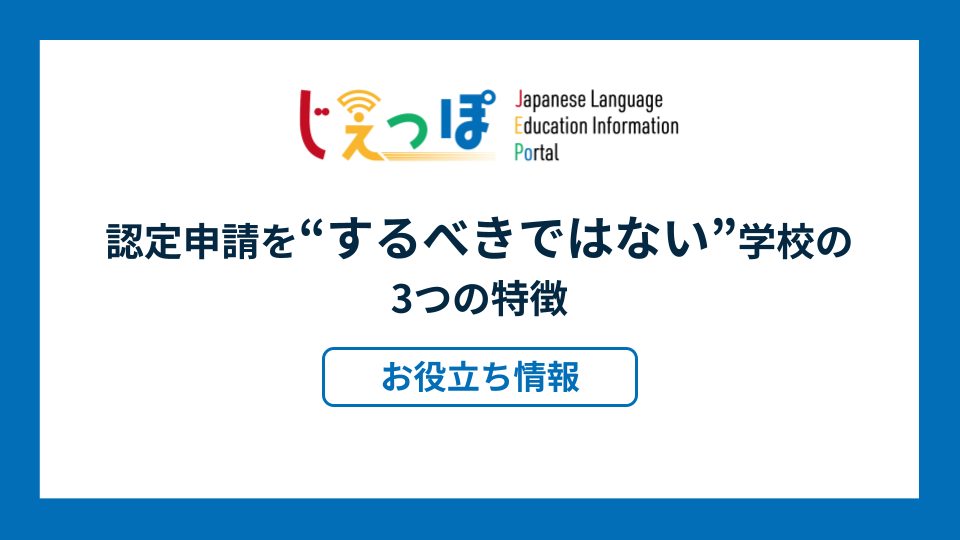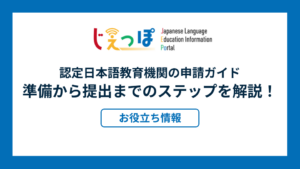制度が始まって以降、「次の期にはうちも申請したい」という声が増えています。
けれど、すべての学校が今すぐ出すべきとは限りません。
書類を整え、人数をそろえても、主任の理解が浅かったり、体制に無理があったり、設置者が「これまでの経験でなんとかなる」と考えてしまう。実際、そうした学校ほど審査で厳しい指摘を受けています。
認定申請は、経験ではなく準備と理解の深さで決まります。
今回は、これまでの支援現場から見えてきた「まだ申請すべきではない学校の3つの特徴」を整理します。
主任の「勤続年数=安心」という思い込み
― 成績評価を“数字で説明できる”主任がいますか?
主任を選ぶとき、つい「教務を長くやっているから」「真面目で信頼できるから」という理由で任命していませんか?
あるいは「3年以上勤務しているから主任になれる」という感覚で決めていませんか?
しかし、認定審査で見られているのは勤続年数ではなく“教育課程を設計・説明できる力”です。
主任は授業の調整役ではなく、学校の教育理念をカリキュラムに落とし込む責任者。
つまり、「何を、どの順番で、どのように教えるか」を理論的に設計し、「なぜそうするのか」を成績評価や学習成果のデータで合理的に説明できるかが問われます。
たとえば、次のような質問に即答できる主任がどれだけいるでしょうか。
- 「この授業で到達させたいレベルを、どの評価指標で測定していますか?」
- 「学期末の成績と出席率・進級率の関係をどのように分析していますか?」
- 「評価結果を次の授業設計にどう反映していますか?」
こうした質問に対して、「感覚的に」や「他校でも同じ教材を使っているから」と答えてしまう主任は少なくありません。
ですが、審査官が求めているのは“説明の筋道”であり、
データや根拠をもとに教育の質を改善していける教育経営の視点です。
主任任命は“信頼できる人”かどうかではなく、構造を理解し、数字で語れる人かどうか。
そこを取り違えると、どんなに書類が整っていても、教育課程の自立性が担保されていないと判断されてしまいます。
認定申請、気になっていませんか?
「うちも申請すべきなのかな…」
「どのコースで申請すればいいか分からない」
そんなお悩みは、制度と実務に詳しいスタッフが無料でご相談を承ります。
(初回ご相談無料・Zoom対応OK)
「必要な人数はそろっている」では通らない
― 体制は“揃えること”よりも“運営できること”が問われます
認定申請では、必要な人数や役職を「書類上そろえる」ことよりも、実際にその体制で運営できるかが厳しく見られます。
よくあるのが、
「専任教員3名、主任・校長も配置済みだから問題ない」
「制度上の基準を満たしているから大丈夫」という考え方です。
しかし、審査で確認されるのは「基準を満たしているか」ではなく、「それが現実的に機能するか」です。制度上定められた専任教員の上限授業コマ数(週20単位時間)はあくまで目安であり、実際の学校運営でその上限に張りつく体制は“現実的ではない”と見なされます。
たとえば、次のようなケースでは、書類が整っていても疑問を持たれる可能性が高いです。
- 全員が経験1年未満の教員で、同じレベル・同じコマ数を担当している
- 10年以上の経験者と新人が、同じ業務分担・同じ時間割構成になっている
- 研修計画が提出されているが、経験差に応じた支援や育成方針が示されていない
こうした場合、審査官から次のような質問が入る可能性があります。
「なぜこのような配置としたのですか?」
「経験差をどう補って指導体制を維持しますか?」
つまり、審査官が見ているのは“数字”ではなく“説得力”です。どんな体制にも理由があり、その理由を合理的に説明できるかどうかが鍵になります。
「求められる人数・役職はそろっているから安心」ではなく、「なぜこの体制が教育の質を支えるのか」まで語れる構成が求められています。
「なんとかなる」と思っていませんか?
― 経験や感覚では、認定審査は乗り切れません
「長年日本語学校を運営してきたし、自分が一番よくわかっている」
「学生のことは現場で見てきた。だから審査でも伝えられるはず」
そう思って、面接の準備を後回しにしていませんか?
これまで多くの申請で、“なんとかなる”と思って本番で答えられなかった設置者を、私たちは何度も見てきました。
認定審査では、書類の正確さや誠実さだけでなく、設置者・校長・主任の三者が「制度の目的をどれだけ理解しているか」が問われます。
つまり、「これまで何をやってきたか」ではなく、「なぜ、どのようにやろうとしているのか」を説明できるかが勝負です。
主任や校長が準備している書類も、最終的に責任を負うのは設置者です。
認定申請は、設置者自身がプロジェクトリーダーとして旗を振らなければ成立しません。
「この書類は何を示しているのか?」
「面接でどんな点を聞かれる可能性があるのか?」
「それに対して、学校としてどんな方針を持っているのか?」
これらを自ら説明できない設置者は、どれほど現場経験が豊富でも、審査官からは“理解が浅い”と判断されてしまいます。
制度は、経験者だからこそ油断しやすい構造になっています。
「なんとかなる」ではなく、「自分が先頭で答えられる状態にしておく」こと。
それこそが、学校の信頼性を支える設置者の最大の役割です。
まとめ ― 焦って出すより、“整えてから出す”方が早い
認定申請は、誰でも出せます。
しかし、通る学校と通らない学校の差は「どれだけ整えてから出したか」に尽きます。
主任の力量も、人員体制の現実性も、設置者の姿勢も、どれも書類では見えない“本質”の部分を審査で問われます。
つまり、「分かっているつもり」で申請してしまうと、その“つもり”が面接で必ず浮き彫りになります。
焦って出しても、結果的に不合格になれば、1年の時間と関係者の労力を失うだけです。
一方で、半年〜1年準備に時間をかけた学校ほど、体制も理念も整理され、審査でも一貫した説明ができています。
認定申請とは、書類を出す作業ではなく、学校としての教育を再設計するプロジェクトです。
出願を遅らせることは「後退」ではなく、「整えるための前進」。
もし今、自校に足りないものが見え始めているなら、その気づきこそが、認定校への第一歩です。
次回申請に向けて、お悩みはありませんか?
- コースの組み立て方が分からない
- カリキュラムが基準を満たしているか不安
- 認定要件をどこまで整備すべきか知りたい
実際の支援経験をもとにご相談に応じています。お気軽にご相談ください。