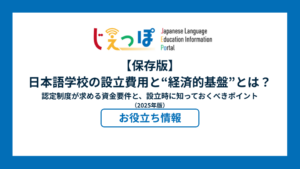ここ最近、「適正校の判定が下がった」「指導を受けた」という学校の声を耳にすることが増えています。
出入国在留管理庁による適正校の選定は、これまで以上に厳格化が進んでおり、特に「著しく不適切な受入体制」と判断されるケースが増えているのが現状です。
この「著しく不適切な受入体制」とは、出席管理や資格外活動、学習状況の把握、人権対応など、留学生の受け入れや在籍管理に関する体制が不十分と見なされる状態を指します。
判断が下されると、改善が確認されるまでの間、上陸基準に適合しない教育機関として扱われ、結果的に適正校の選定から外れたり、クラスⅡへの降格といった影響を受ける可能性があります。
こうしたリスクは、必ずしも悪意や重大な違反からではなく、「忙しさで届出が遅れた」「管理が属人的になっていた」といった日常の見落としから生じることが少なくありません。
本記事では、実際にどのような体制が問題とされているのか、そして学校運営の現場でどんな点に注意すべきかを整理していきます。
「著しく不適切な受入体制」とは
「著しく不適切な受入体制」とは、留学生を受け入れる教育機関としての基本的な管理体制が整っていない状態を指します。
これは出入国在留管理庁が令和6年4月に策定した指針で、在留資格「留学」における上陸基準のうち、「教育機関の受入体制が適正であること」を判断するための具体的な基準として位置づけられています。
つまり、この指針は単なる注意喚起ではなく、在留資格の許可や適正校の選定に直接関わる“審査基準”です。
教育機関がこの基準に適合していないと判断された場合、その学校は「上陸基準に適合しない教育機関」として扱われ、新規留学生の受け入れが事実上停止されたり、適正校の判定が下がるなどの影響を受けることになります。
さらに、改善が確認されるまでの間は、在留審査の際にも不利な扱いを受ける可能性があります。
言い換えれば、「著しく不適切」と判断されることは、学校の信用や経営の安定性に直結する重大なシグナルなのです。
まずはお気軽にご相談ください
初回ヒアリングは無料。契約を前提としない情報交換からでも大歓迎です。
判断される主な5つのケース
出入国在留管理庁の指針では、「著しく不適切な受入体制」と判断される主なケースを5つに分類しています。
いずれも留学生の出席や学習、生活状況を教育機関がどのように把握・管理しているかという観点から整理されています。
| 分類 | 不適切とされる状況 | 現場で起きがちな例 |
|---|---|---|
| 1. 出席管理 | 出席率・退学者の把握が不十分で、改善されていない | 欠席報告の遅延、休学の扱い未整備、行方不明者の対応不十分 |
| 2. 資格外活動管理 | アルバイト状況の確認・指導を怠る | 許可範囲超過を把握できていない/週28時間超を黙認 |
| 3. 学習状況・体制管理 | 日本語力・経費支弁・受入規模のバランスが不適正 | 定員増に伴う教員不足、日本語能力の確認不足、仲介者への報酬支払状況の管理不足 |
| 4. 人権侵害・法令違反 | パスポートの取り上げ、暴言、セクハラなど | 教職員教育不足による不適切対応 |
| 5. 改善措置の未実施 | 問題学生が多く、是正が行われない | 在籍率低下や放置による「改善見込みなし」と判断されるケース |
これらの項目は、どれも教育の現場で起こり得る事象ばかりです。
一度「著しく不適切」と判断されると、改善が確認されるまでの間は上陸基準に適合しない教育機関として扱われ、新規学生の入国許可や在留期間更新にも影響が及ぶ可能性があります。
つまり、日々の在籍管理・教職員体制・情報共有の仕組みこそが、学校の信頼を守る第一歩なのです。
適正校判定との関係
「著しく不適切な受入体制」と判断されることは、適正校の選定結果に直結する重要な要素です。
入管庁が定める基準のうち、「在籍管理上不適切であると認められる事情がないこと」という項目に該当しなくなるため、指導を受けた学校は次回の選定で不適合またはクラスⅡ扱いとなる可能性があります。
一度の指導でも、翌年度の評価に影響するだけでなく、クラスⅠ維持の条件である「3年間連続の適正校」「指導歴なし」も満たせなくなります。
その結果、学生の在留資格申請で提出書類の簡素化が受けられないなど、事務手続き・募集活動の双方に支障をきたすことがあります。
つまり「著しく不適切な受入体制」は、単なる運営上の注意ではなく、学校経営の信頼性を左右する評価項目といえます。日常の在籍管理や体制運用を「審査対象の一部」と意識して整えることが、適正校維持の最大のポイントです。
学校として今すぐ確認すべきポイント
「著しく不適切な受入体制」とみなされる多くのケースは、実は特別な違反ではなく、日常の管理や連携の小さな抜けから生じています。
次の5点を中心に、基本を丁寧に見直すことが大切です。
出席・在籍管理
欠席理由や行方不明者の記録を正確に残し、全職員で共有できる仕組みを整える。
資格外活動の確認
学生の自己申告だけに頼らず、就労先や時間数を定期的にチェックする。
教員・体制の適正化
定員や授業数の変化に応じて配置を見直し、無理のない指導体制を保つ。
受入時の確認
日本語力や経費支弁能力を形式的にせず、エージェント関与も記録化しておく。
早期対応
指摘やトラブルがあった際は、改善と報告を迅速に行う。
日々の基本的な管理を積み重ねることが、結果的に学校の信頼と安定した経営につながります。
まとめ
「著しく不適切な受入体制」という言葉は、少し堅い印象がありますが、その本質は「留学生一人ひとりを適切に支える体制が整っているか」という問いかけです。
出席、学習、生活、就労──どれも学校の日常業務の延長線上にあるものばかり。
特別な取り組みよりも、小さな管理の徹底と情報共有の仕組み化が最も効果的です。
一度の指導や管理不備が、適正校判定や在留手続きに長く影響する時代になりました。
だからこそ、今のうちから体制を点検し、改善を積み重ねることが重要です。
学校運営に不安や疑問がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
日本語学校に関するご相談はこちらから
まずは無料相談お申込みをクリック!
状況をお伺いし、戦略のご相談をさせていただきます。